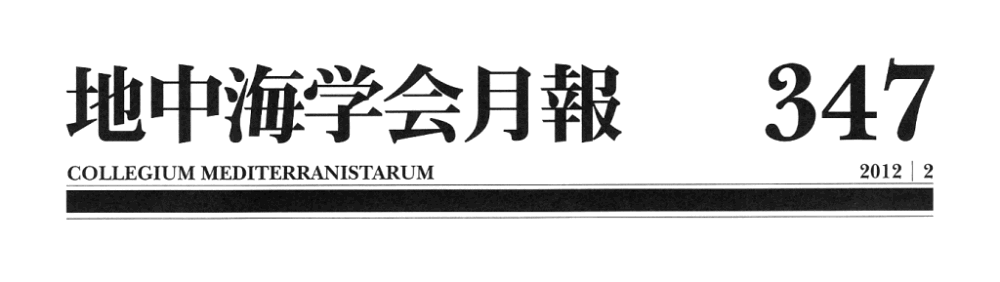

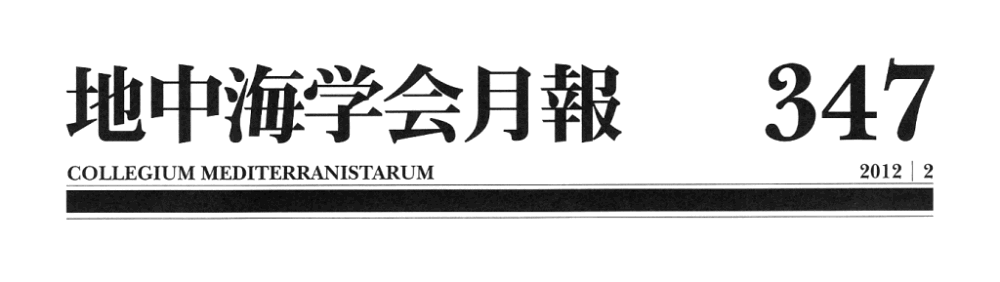

学会からのお知らせ
* 4月研究会
下記の通り研究会を開催します。
テーマ:初期アルメニア正教教会堂建築におけるドーム架構の展開
発表者:藤田 康仁氏
日 時:4月14日(土)午後2時より
会 場:東京芸術大学美術学部中央棟1階第2講義室(最寄り駅「上野」「鶯谷」「根津」 http://www.geidai.ac.jp/access/ueno.html)
参加費:会員は無料,一般は500円
数多くの遺構を今日に残しているアルメニア正教教会堂建築(アルメニア建築)は,アナトリアからコーカサス一帯における建築文化を考える上で重要な遺構群と捉えられるが,これまでその特質は十分明らかにされてこなかった。本発表では,アルメニア建築に多用されるドーム架構に注目し,特に初期アルメニア建築の特質を明らかにするとともに,この地域における初期アルメニア建築の史的意義について考察する。
* 第36回大会
第36回地中海学会大会を6月16日,17日(土,日)の二日間,しまなみ交流館(広島県尾道市東御所町10-1)において下記の通り開催します(予定)。詳細は決まり次第,ご案内します。
6月16日(土)
13:00〜13:10 開会宣言・挨拶
13:10〜14:10 記念講演
「地中海と瀬戸内海──島の歴史と伝承と」
樺山 紘一氏
14:25〜16:25 地中海トーキング
「崖に住む」(仮題)
司会:野口 昌夫氏
16:30〜17:00 授賞式
地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞
17:10〜17:40 総会
18:00〜20:00 懇親会
6月17日(日)
10:00〜12:30 研究発表
13:30〜16:30 シンポジウム
「海の道──航路と文明」(仮題)
司会:末永 航氏
* 会費納入のお願い
今年度会費(2011年度)を未納の方には本号に同封して請求書をお送りします。至急お振込みくださいますようお願いします。ご不明のある方,学会発行の領収証を必要とされる方は,お手数ですが事務局までご連絡ください。
なお,新年度会費(2012年度)については3月末にご連絡します。
会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円
振込先:口座名「地中海学会」
郵便振替 00160-0-77515
みずほ銀行九段支店 普通 957742
三井住友銀行麹町支店 普通 216313
* 常任委員会
・ 第2回常任委員会
日 時:2011年12月10日(土)
会 場:東京芸術大学上野キャンパス
報告事項:『地中海学研究』 XXXV (2012) に関して/研究会に関して/ブリヂストン美術館秋期連続講演会に関して/NHK 文化センター企画協力講座に関して/知求アカデミー企画協力講座に関して 他
審議事項:第36回大会に関して/地中海学会賞に関して/地中海学会ヘレンド賞に関して
訃報 2011年12月24日,会員の辻佐保子氏(2003年度地中海学会賞受賞)が逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
|
研究会要旨 東プロヴァンスの教会遺構と彫刻 ──古代都市リエズに残される初期中世の史料を中心に── 10月1日/東京芸術大学 |
アルプスと地中海を結ぶ交通の要所に位置するリエズ (Riez, Civitas Reiensium)は,ケルト=リグリア時代から古代,中世を通じ,さらに18世紀末まで,この地域の中心都市であった。しかしフランス革命以降1960年代まで人口は減少を続け,現在では住民1,700人ほどの小規模な町である。19〜20世紀の町の衰退は,県庁所在地であるディーニュの発展とは好対照をなしている。リエズの現在の産業の主軸は観光であり,周辺の観光地──陶器で有名なムスティエ・サント・マリー,ヴェルドン渓谷の自然公園,保養地のグレウーなど──と結びついた観光コースの一環として,夏にはそれなりに多くの観光客が訪れる。一方,シーズンオフには町は閑散とした様相を見せ,冬場に途絶える観光を活性化させることが市行政の大きな課題となっている。2004年から2011年まで,カミーユ・ジュリアン研究所研究員フィリップ・ボルガールの主導により,古代都市リエズをめぐる共同研究プログラムが実施されたが,このプログラムは,その発動当初より,町の文化財再生計画と連携していた。リエズとその周辺地域に残される考古遺跡・歴史遺物を観光の主眼として再開発することを目的とし,古代都市としての価値を高めるために,大浴場遺跡(およびその上に建設された大聖堂遺跡)の発掘・整備,遺跡公園の建設,歴史建造物に指定されているマザン館(16世紀)への新博物館の創設などが,文化財再生の主要プロジェクトとして計画された。博物館の創設準備と平行し,私は特に初期中世の石造彫刻の研究を担当してきたが,現在これら共同研究プログラムは最終段階をむかえている。
古代のリエズの町は,14世紀後半の城壁に囲まれた現在の市街地の西,コロストルとオヴェストルの二つの川に挟まれた地区に広がっていた。リエズの司教座の創設時期は不明だが,最初に知られている司教はマクシムス(427年以前〜452年以降)であり,439年には宗教会議が開かれている。マクシムス後,650年までは,ほぼ総ての司教の名(7人)が知られているが,一方で7世紀後半から10世紀までの期間,リエズについて語る史料は大変少ない。この時代,おそらく司教座聖堂は現在の市街地を北東に見下ろすサン・マクシムの丘の上に移されたと推定される。ケルト=リグリア時代にオピドゥム(城塞都市)があったと考えられているこの丘の上には,1662年建設のサン・マクシム聖堂がそびえ,その内陣に6本の古代の柱が使われている。いまだ本
格的な発掘調査がこの場所に行われたことはなく,リエズの初期中世について未解決の疑問が数多く残されている。
最初の司教座聖堂(5世紀)は,ガリア・ナルボネンシスでも最も大きな浴場の一つに数えられるフラウィウス朝時代の建築複合体の跡地に建てられた。この聖堂は1500年頃に壊され,石材は城壁沿いに建てられた新しい大聖堂の建設に使用されたが,一方,聖堂に付属した洗礼堂は礼拝堂として残された。17〜18世紀,この集中式プランの礼拝堂は,古代の神殿であったという伝承から「パンテオン」と呼ばれ,コロストル川岸に立つ4本の古代柱とともに,古代都市リエズを象徴する存在として知られていた。これらの古代モニュメントを描いた水彩画やスケッチが多数残されている。19世紀後半にリエズの市長であり古代愛好家であったベンジャマン・マイエの発掘によって礼拝堂の床から洗礼槽が発見され,1930年には郷土の学者マルセル・プロヴァンスの主導によって,礼拝堂内に彫刻博物館が創設され,散逸していくばかりであった古代・中世の石造遺物が堂内に収集された。司教座聖堂は1960〜70年代,さらに2005年から発掘調査が実施され,その建築プランのおおよそが明らかになっている。ただし,ロマネスク時代の大改築とその後の破壊により,初期中世の内部空間の変遷の痕跡はほぼ失われており,文字史料も限られる中,発見される石造遺物は,たとえ元のコンテクストを失った断片的なものであっても,この時代の数少ない重要な資料となっている。
リエズの初期中世の彫刻については,1930年の彫刻博物館のコレクション,1960〜70年および2005〜2011年の司教座聖堂遺跡発掘調査での出土遺物,さらに共同研究プログラム枠内での現地調査により,考古遺物倉庫や町の壁などから発見されたこれまで未報告の遺物などが研究資料となった。美術館学芸員ファビエンヌ・ガリスと共同してカタログを作成するとともに,それぞれの遺物の形態,装飾,機能の分析を行ったが,イタリア産大理石と地元石灰岩を用いた丁寧な造作,動物模様の多用,さらに,断片に残されている用途断定に有用な痕跡の多様さに特徴付けられる。東プロヴァンスの他の古代都市,ディーニュやフレジュスの大聖堂から出土している遺物との比較により,この地方の初期中世の石造遺物の特徴がさらに浮き彫りにされる。
|
ビザンツ皇帝とムスリムの使者 |
981/2年,ブワイフ朝君主アドゥド・アッダウラの使者としてビザンツ皇帝バシレイオス2世の許へ遣わされた人物がいる。バーキッラーニー(1013年没)という,マーリク派法学及びアシュアリー派神学を修め,バグダード近郊のカーディー職を務めた人物である。この方,持ち前の頭脳を活かして皇帝の舌を巻かせる,という話が伝えられている。その概要は,神にのみ跪拝するムスリムのバーキッラーニーを額突かせようとした皇帝が,腹這いにならなければ通れないほど低い入口を設けて謁見の間に召し出す。皇帝は,彼がその入口から腹這って入ってくることで,自らに跪拝したと見なそうとしたのである。すると,彼は入口の所で背中を見せ,四つん這いになり,尻からその入口を通って,皇帝の前まで進み,立ち上がってくるりと前を向く,というものである。
この逸話はバーキッラーニーの機知に富むさまを伝えるものとして,古くはバグダーディー(1070年没)著の『バグダード史』に示されている。逸話としては面白いが,こちらが知りたいのは,如何なる用向きでビザンツ皇帝の許に派遣されたのか,である。だが,その内容は伝わっていない。彼の後にビザンツ帝国に派遣された人物の事例を伝えるルーズラーワリー(1095年没)の史書にバーキッラーニーの事例が若干伝わっており,領土問題についての使者であったことが推測できる程度である。
そんな折,偶々『ヨーロッパ文化史研究』10号(2009年)所収,根津由喜夫氏の論文「10世紀コンスタンティノープルのアラブ人」を読む機会を得た。同論文には,後ウマイヤ朝の君主アブドゥッラフマーン2世によってビザンツ皇帝テオフィロスの許に派遣されたガザール(864年没)の逸話が示されている。驚いたことに,両者の会見の様子がバーキッラーニーのものとほぼ同じである。100年近く離れているとはいえ,ビザンツ皇帝がアラブの使者に同じ手口でやり込められる事態が二度も起きるとは思われない。とすると,10世紀の人であるバーキッラーニーの逸話はガザールの逸話の二番煎じなのだろうか。そこで,ガザールの逸話の出典について少し検討してみようというのがこの小文の目的である。
根津は Byzantion 誌12号(1937年)所収の Lévi-Provençal の論文に依拠している。同論文には17世紀のマグリブの歴史家マッカリーの史書を典拠として挙がっている。かなり後世の史書であるが,イブン・ハイヤーン(1071年没)の史書並びにイブン・ディフヤ(1235年没)の詩人
伝を典拠とし,特に前者はバーキッラーニーの出典『バグダード史』と年代的に重なる。
しかし,マッカリーが引用するイブン・ハイヤーンの記事には,ガザールがビザンツに赴いたとはあるが,件の謁見の逸話はない。またイブン・ディフヤからの引用では,東方への派遣と共にマジュース Majūs の国への派遣も伝えているが,やはり謁見の逸話は存在していない。では Lévi-Provençal は何を根拠としているのだろうか。そこで,今度はイブン・ハイヤーンとイブン・ディフヤそれぞれの史書にあたってみると,前者の現行の校訂本では該当箇所が見つからず,手詰まり。写本にまで戻って確認せねばならない。後者を見ると,マッカリーの引用元とは別の箇所に,バーキッラーニーと同じ逸話が収録されている。ただし,謁見の相手はビザンツ皇帝ではなくマジュースの王である。
マジュースとは元来,拝火教徒を意味するが,この場合844年頃,イベリア半島西部に来寇したノルマン人を意味していると思われる。つまり,イブン・ディフヤは,ガザールの派遣先をノルマン人の国とし,かの地で件の逸話の通りの謁見が行われたというのである。
イブン・ハイヤーンの史書の確認作業が残っているが,「ビザンツ皇帝」と「マジュースの王」の二説あることが判明した。Lévi-Provençal は,イブン・ディフヤがマジュース来寇とガザールのビザンツへの派遣が同じ年にあったため,二つの出来事を混ぜ合わせてしまったのだと理解している。ただ,Lévi-Provençal は,イブン・ディフヤの詩人伝は確認しているが,イブン・ハイヤーンの史書を確認してはいないようなので,そもそもその逸話を伝えていないマッカリーに依拠して,ガザールの謁見相手がビザンツ皇帝であるとする彼の根拠は乏しいと言わざるを得ない。
以上,イブン・ハイヤーンの記述次第ではあるが,古くは11世紀の史料において,地中海を挟んで東と西の地からビザンツ帝国に赴いた二人の使者に共通の逸話があることが判明した。根津論文には,この逸話の原型として10世紀のイタリアの逸話を指摘する研究が挙げられている。バーキッラーニーの事例が存在するということは,その逸話のモチーフが地中海を離れてイラクまで達していたということになるが,さて,紙幅が尽きた。機智で王をやり込めるこの話,時代・地域の広がりを予想させるのだが,別の説をご存知の方はご一報ください。
|
「王の死刑執行人」の娘の自伝 |
2011年6月に開催された第35回大会の地中海トーキング「地中海の女」で,レオノール・ロペス・デ・コルドバ(1362/63-1430?)の『回想録』について話す機会をいただいた。
レオノールは,カスティーリャ王ペドロ1世の側近だったマルティン・ロペス・デ・コルドバの娘だった。王宮で生まれてペドロ1世の家族と共に育ち,恵まれた幼少時代を送ったが,第1次カスティーリャ継承戦争によって運命は一変した。ペドロ1世の異母兄エンリケ・デ・トラスタマラが勝利したこの戦争で父方の近親者の殆どと財産を失ったレオノールは,母方の親族の庇護のもと苦難に満ちた前半生を送った。その後,人生の半ばで再びレオノールは権力の中枢に身を置くことになった。ペドロ1世の孫ランカスター公女カタリーナがエンリケ2世の孫エンリケ3世と結婚し,レオノールを側近として取り立てたのである。エンリケ3世が早世しフアン2世がわずか1歳で即位すると,レオノールは摂政カタリーナの側近として政治を牛耳るようになった。しかし,自らめぐらした権謀術数が命取りとなり,レオノールはカタリーナ自身の命により宮廷を追放され,歴史の表舞台から姿を消した。
『回想録』は,宮廷入りするまでの前半生を,おそらく宮廷からの追放直後にレオノールが口述筆記させたものである。カスティーリャ語(スペイン語)散文における初めての自伝的作品であると同時に,著者が同定されている初めての女性による作品でもある。レオノールの語りは,失われた名誉と財産,および,これらの回復をめぐって展開する。遺恨と希望の間を行き来する感情の振幅を,レオノールは時には切々と,時には熱っぽく語る。何よりも特徴的なのは,レオノールの語りには常に,異様ともいえるほどの緊張感が漲っていることである。
以上のようなことを地中海トーキングでお話した後,受付におられた方たちと話していたところ,青池保子作の漫画『アルカサル──王城』(以下『アルカサル』とする)の話題が出た。そのうえ,『アルカサル』文庫版(全7巻)の解説者のうち4名が地中海学会員で,その4名のうち2名がその場におられたのだった。その瞬間,私は「やはり」と思った。実は地中海トーキング前夜に『アルカサル』の人気のほどを思い出し,愛読
者の方から質問がありはすまいかと少し心配していたからである。
『アルカサル』は,ペドロ1世を主人公とし,1984年から94年までの雑誌連載と2007年の読み切り2編で完結した長編漫画である。私は学生時代からこの漫画の評判を耳にしつつも長いあいだ手に取ったことはなかった。しかし,2年前にある中世研究者から,「人口に膾炙している」とでも言うべき人気のほどをあらためて聞かされたのをきっかけに,文庫版を全巻買い,400頁前後×7巻を一気に読んだ。読後はもちろん疲れ果て,この漫画のネーム作りは NHK 大河ドラマの脚本執筆より困難だったかもしれないと思ったり,時代考証の大変さを想像したりして,作者・青池保子さんの力量に感服した。
『アルカサル』において,レオノールの父マルティン・ロペス・デ・コルドバはペドロ1世と対をなす存在として描かれている。自信と活力に満ちた太陽の如きペドロ1世にあくまでも忠実なマルティンは,廉直,寡黙で驕りを知らない月のような存在で,「王の死刑執行人」の異名を持つ。このようなマルティンに近づく女性はおらず,マルティンも女性に興味を示さないが,他ならぬペドロ1世の形だけの妻ブランシュがマルティンを密かに愛するようになる。そして,死ぬ間際のブランシュから愛を告白されたマルティンは,ショックのあまり修道院に籠ってしまうという純情な堅物ぶりを示す。このようなマルティンは,文庫版解説から察するに,『アルカサル』愛読者の間で高い人気を博している。
上のようなロマンティックなマルティン像は,青池さんが参考にされた P. メリメの『カスティーリャ王ドン・ペドロ1世伝』で描かれたものであろう。実際のマルティンには,妻と少なくとも1人の愛人がおり,レオノールをはじめ6人の子がいた。私は,地中海トーキングの前夜に慌てて『アルカサル』を取り出して,漫画のマルティンは生涯独身で,レオノールも漫画には登場しないことを確認し,『アルカサル』愛読者からは質問が出ないだろうと安堵してトーキングに臨んだのだった。しかし,トーキング後に,私の発表ははからずも『アルカサル』のマルティン・ファンを幻滅させてしまったことがわかった。そして,たいへん申し訳なく,畏れ多いことをしてしまったとまで思いつつその日を終えたのだった。
|
レオナルドの《大洪水》 |
ロンドン郊外のウィンザー王立図書館に所蔵されているレオナルド・ダ・ヴィンチの素描には,彼が最晩年に描いたとされる《大洪水》計16点が含まれている。それらは,1985年に東京,池袋の西武美術館で「レオナルド・ダ・ヴィンチ素描展」が開かれた際に展示され,筆者もそれを見ることができた。ずいぶん昔のことで,当時筆者はまだ学生であったが,その時はレオナルドがどういうつもりで大洪水を描いたのか理解できず,釈然としない思いが残ったことを覚えている。
《大洪水》シリーズに描かれているのは,すべてを破壊し,呑み尽くす水と風の名状しがたい圧倒的な暴力である。洪水は人々や動物を襲い,木々をなぎ倒して呑み込み,都市を破壊し,岩山を倒壊させる。人間の姿はごくわずかに,チョークやペンのラフなタッチでそれとわかる程度に描かれるに過ぎない。このような自然の猛威の前では,人間は全く取るに足らない,無に等しい存在である。このような嵐や洪水をレオナルドは実際に見聞したのであろうか。《大洪水》のうち何点かは1515年にベッリンゾーナで起きた洪水に想を得たとも言われるが,しかし《大洪水》のどの紙葉にも特定の出来事との関連をうかがわせる要素は見当たらない。むしろ,自然の暴力を能う限り描き出そうとしながらも,レオナルドの手は象徴的な形態へと向かいがちである。
レオナルドの自然への関心はごく初期からのものである。《受胎告知》やヴェッロッキョとの共作になる《キリストの洗礼》の背景に描かれた風景がそれを物語る。15世紀後半のフィレンツェの画家たちは多かれ少なかれ型にはまった似たような風景を描いているが,この二点でレオナルドが描いた風景は異なる。彼が描くのは湿潤な空気にかすむ岩山と川ないし湖で,それらは見る者に古代ローマの壁画や中国の山水画さえも連想させる。同様な風景は《岩窟の聖母》や後年の《聖母子と聖アンナ》,《モナ・リザ》にも見出され,レオナルドにとって重要なモティーフであったことがわかる。自然,中でも水の動きに対する関心が並々ならぬものであったことは,レスター手稿の数々の記述にも明らかであり,晩年に至るまでそれは一貫していたと言える。したがって水の動きへの関心が大洪水の素描へとつながったことは想像に難くない。
レオナルドの水の研究の根底にあるものは四大元素であるという。水は重力の中心に対して球形をなす。したがって地球上の水は高いところにあるものは下降し,低
いところにあるものは上昇して一定になろうとする力を潜在させている。大地には高所と低所,すなわち山と谷があるが,これらもまた水と同様に重力の中心に対して一定の高さになろうとする力を潜在させている。水の球と大地の球,両者の均衡を求める潜在力が破局をもたらす。レオナルドはどうやらこのように考えたらしい。そこにはアリストテレスの影響があると指摘されている。こうした考察や実地調査からレオナルドが,高山で発見される化石がノアの大洪水によってもたらされたという当時の常識を否定するに至ったことはよく知られている。
《大洪水》の素描は晩年の数年間に集中している。多くはレオナルドがローマに滞在していた頃からフランスのアンボワーズで死を迎えるまでの期間に制作された。そのため,レオナルドがミラノからローマへ移住した1513年に,その頃完成したばかりのシスティーナ天井画の《ノアの大洪水》を見たことがきっかけとなっているのではないかという向きもあるが,筆者はその意見には同調しかねる。と言うのもミケランジェロの関心はあくまでも人間にあり,レオナルドの関心とは対蹠的であるからである。
いずれにせよ,こうした考察はそれぞれに啓発的ではある。しかし結局のところ《大洪水》の周囲をぐるぐる回るだけで,肝心要のことを避けて通っているのではないだろうか。美術史的な考察は作品の表層にとどまり,レオナルドの内面に深く踏み込んで創造の核心にまで至るような体のものではないのではないか,と思わざるをえない。このような終末の幻想がいったいどこからレオナルドに来たったものかという本質的な問い,それに対する最終的な解答にはなっていないと筆者には思われてならないのである。ミケランジェロと異なり,レオナルドは死後の復活も最後の審判も信じていなかった。あらゆるものを呑み込み,崩壊させる水の脅威が,一切の救いのない,完全なる終末をもたらすという恐るべき幻想に対して,レオナルド自身は何を思っていたのだろうか。
3月11日の地震と津波をテレビ越しではあるが目の当たりにした時,筆者にはレオナルドの幻想が現実の惨劇となったかのように思われた。それ以来,あれほどの終末の幻想をどんなつもりでレオナルドが描いたのか,できることなら本人に問い質したいという思いにしばしば駆られるのである。
|
江戸の地中海 |
ヨーロッパ中世の音楽史を専攻している私が,何の因果か,山口県の自治体史編纂に携わっている。こんなことを書けば,さも「日欧交流」を担っているようで聞こえがよいが,要は東大史料編纂所の保谷徹先生から送られてくる英語やフランス語の史料を翻訳したり,筆耕するアルバイトである。とはいえ,歴史家のさがで,思わず読み耽ってしまうことも少なくはない。
扱っている史料はおもに幕末維新期に日本に滞在した外国公使や軍人が記した報告書である。周知のように,1858年に江戸幕府は,アメリカ,イギリス,オランダ,フランス,ロシアといった「列強」と通商条約を結ぶ。いわゆる「安政五ヵ国条約」と呼ばれるものである。しかし,これが天皇の「勅許」を得ずに大老井伊直弼の独断で行われたため,攘夷派の反感を買い,「安政の大獄」や「桜田門外の変」といった事件が起こる。だが,幕府も上記の諸条約の条項をすぐさま実行した訳ではなく,のらりくらりとした対応で,できる限り条約の履行を先延ばししようとしていた。
横浜の居留地にいた列強の代表は「大君政府」のこうした対応に業を煮やしていた。彼らの不満は度重なる外国人殺傷事件により爆発する。特に「生麦事件」(1862年)では,イギリスの代理公使ニールは幕府に対して賠償を強く求めた。幕閣の議論は因循を極め,外国行使への対応はおざなりであった。これに関して,私が読んでいるフランス領事館の史料では,次のような厳しい文言が並ぶ。「(日本の貴族は)きわめて慎重で,忍耐強く,根気があり,不可思議で,形式にこだわり,決断が遅く,裏表が激しく,議論において説得が必要と感じている間は頑固であり続ける」。また,彼ら武士は「書面による議論から口頭にそれに移らなければならない時は,侮蔑的な沈黙,空虚な理屈,巧みな捏造,その場しのぎの豊富な施策などによって,最高に鍛えられた忍耐力を示す。彼らは,結論を出さずに,そして自分たちの心の底を見せずに,数日間ぶっ通しで議論することができるのである」(SHM GG 2-40-8)だという。昨今の賑々しい「日本人論」と通ずるであろうか。結局,幕府はイギリスに対して賠償金を払い,日英断交の危機は回避された。
むろん,実際の幕府の政策はそう単純なものではなく,外国人に対する強行な姿勢を攘夷派へアピールしつつ,戦争回避を画策するものであったらしい(保谷徹『幕末日本と対外戦争の危機』参照)。いずれにせよ,列強諸国の代表らは徐々に強
行策に傾き,その姿勢は長州藩による「攘夷実行」──外国船舶砲撃事件──に対する四国艦隊による報復攻撃,いわゆる「下関戦争」(1863/64年)に現れるわけである。列強による攻撃がたんなる「報復」なのか,あるいは日本の占領を意図したものなのかについては,議論があるらしい。しかし,軍人らの報告書を読むと,かなり正確な地図や地理に関する知識があり,彼らの本気度に驚かされる。その反面,日本の政治情勢に関しては,幕府の組織についてはある程度はわかっていたようだが,複数の老中を混同していたり,風説を鵜呑みにしていたりと捧腹絶倒の記事も存在する。こうした「理解」と「誤解」の間隙を縫うのが,文化交流史の醍醐味であろう。
ところで,下関戦争に関する史料を読んでいると,当時の瀬戸内海の活況が鮮やかに目に浮かぶ。例えばフランス公使レオン・ロッシュはこう記している。「毎日,500から1,000隻のジャンク船が潮とともに[瀬戸]内海に入り,あらゆる工芸品と農産物,とりわけ日本の大衆の二大食材である米と塩漬の魚を輸送する。海上運輸は日本の国民とって必要不可欠なのである……」(SHM GG 2-40-8)。ヒトとモノがさかんに行き来する瀬戸内は,さしずめ「江戸の地中海」だったのであろう。列強の「力づくの政策」は続き,1865年における兵庫沖での示威行動によって朝廷は条約の勅許を余儀なくされ,日本の政局は「攘夷」から「倒幕」に移っていくのである。
さて,幕府は条約履行の延期と列強政府に願い出るため,1861年に38名のサムライを欧州に派遣している。いわゆる「文久遣欧使節団」というものである。一行は12月23日に品川を発つと,香港,シンガポール,ガールを経て,アデンから紅海に入り,まだスエズ運河は開通していないので,汽車でアレクサンドリアへ向かった(その間,日本人としておそらく初めてピラミッドを見る)。地中海に入るとマルタ島を経て,1862年3月5日にはマルセイユに到着。そこからは汽車でフランス,イギリス,オランダ,ドイツ,ロシア(プロセイン),ポルドガルを歴訪した(宮永孝『幕末遣欧使節団』参照)。使節団の目的には条約交渉の他に「夷情探索」というものもあり,使節団には幕閣の他に,福沢諭吉などの翻訳方の武士も同行していた。そこに含まれる医者の箕作秋坪は,東京帝国大学の西洋史学研究室を開いた箕作元八の父である。
表紙説明 地中海世界と植物 24
チューリップ / 太田 敬子
チューリップといえばオランダというイメージが強いが,元来はイスラーム世界からヨーロッパに伝わった花である。オスマン朝領域やイランではラーレ(ペルシア語起源)と呼ばれ,現代トルコ語でもラーレ lâle と言われる。チューリップの語源は,オスマン・トルコ語の tülbend (ターバンの語源と同じくモスリンや紗などの布)から派生したと考えられ,さらにペルシア語の dulband (頭に巻く頭巾)に遡るという。
チューリップはオスマン朝時代に愛好され,モスクの装飾の意匠やスルターンの衣服の模様にも使われた。この花をヨーロッパに紹介したのは,16世紀半ばに神聖ローマ皇帝フェルディナンド2世が派遣したオスマン朝大使ド・ビュスベックであり,彼がスルターンの宮廷からオーストリアにこの花を持ち込んだ。しかし,その栽培が盛んになったのはオランダであった。植物学者クルシウスが1593年にライデン大学に招聘され,そこでこの花の栽培と研究を進めた結果,17世紀になると植物愛好家たちの間でチューリップ人気が高まり,珍しい品種の値段が高騰した。それがヨーロッパ各地に広がり,投機家も参入するチューリップ・バブルとなる。
一方オスマン朝では,ヨーロッパから逆輸入する形で新たなブームが起こり,それは最も贅沢に展開していった。スルターン・アフメト3世(在位1703〜30)はチューリップを愛好し,トプカプ宮殿内にその花壇を造ったことで知られる。当時のオスマン朝宮
廷では軍事的な後退が自覚され,領土的野心が希薄になる中,快楽と美を探求する文化への関心が高まっていた。チューリップの花はその雰囲気を象徴する存在となった。その流れの中で,1718年にアフメト3世がネヴシェヒルリ・イブラヒム・パシャを大宰相に任命してから30年にスルターンが退位するまで,いわゆる「チューリップ時代(ラーレ・デヴリ)」が花開く。アフメト3世とイブラヒム・パシャは積極的に文芸や芸術を保護し,華美な文化が興隆した。細密画家レヴニーが活躍したのもこの時代である。チューリップ・ブームはイスタンブルの「ラーレリ・モスク」に見られるような優雅な建築様式を生み出し,フランスのロココ様式の影響を受けた西洋趣味の文化が流行,ネディームらの宮廷詩人がチューリップの風雅さを歌い上げた。新種開発も盛んに行われ,登録品種は839種に及び,球根の高騰を防ぐために公定価格が設定されたという。表紙は17世紀半ば頃のイズニク製白地多彩文皿(中近東文化センター附属博物館)で,数種類の花が非対称的に描かれ,周円にはチューリップと八弁の花が巡っている。イズニク陶器ではチューリップだけでなく,ヒヤシンス,矢車草,カーネーションなどの草花の意匠が好まれたという。(出典:古代オリエント博物館・松岡美術館・横浜ユーラシア館編『シルクロード 華麗なる植物文様の世界』山川出版社 2006 49頁)