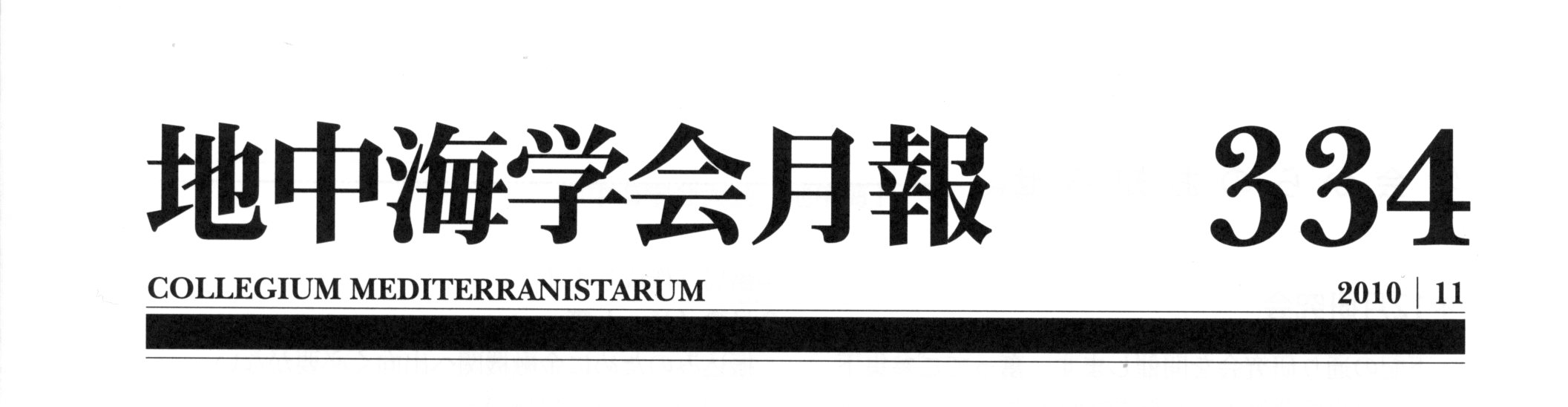| *12月研究会 下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。 テーマ:15世紀ヴェネツィアの地図制作と美術 ──《フラ・マウロの世界図》〈地上の楽園〉にみる 発表者:佐々木 千佳氏 日 時:12月11日(土)午後2時より 会 場:東京芸術大学赤レンガ1号館2階右部屋(音楽学部敷地内 最寄り駅「上野」「鶯谷」「根津」http://www.geidai.ac.jp/access/ ueno.html) 参加費:会員は無料,一般は500円 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には振込用紙を本号に同封してお送りします。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡ください。振込時の控えをもって領収証に代えさせていただいております。学会発行の領収証をご希望の方は,事務局へお申し出ください。 会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2011年度会費からの適用分です)。 会費口座引落:1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度(2010年度)入会された方には「口座振替依頼書」を月報本号(334号)に同封してお送り致します。 |
会員の方々と事務局にとって下記のメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。 会員のメリット等 振込みのために金融機関へ出向く必要がない。 毎回の振込み手数料が不要。 通帳等に記録が残る。 事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。 「口座振替依頼書」の提出期限: 2011年2月23日(水)(期限厳守をお願いします) 口座引落し日:2011年4月22日(金) 会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とは今回お送りした封筒の宛名右下に記載されている数字です。 なお3枚目(黒)は,会員ご本人の控えとなっています。事務局へは,1枚目と2枚目(緑,青)をお送り下さい。 *新会員名簿 会員名簿(2010年11月15日現在)ができあがりましたので,本号に同封してお送りいたします。 変更事項がある方は,事務局へご連絡下さい。次回作製の折に訂正いたします。 *常任委員会 ・第1回常任委員会 日 時:10月23日(土) 会 場:東京芸術大学上野キャンパス 報告事項:第34回大会及び会計に関して/研究会に関して/NHK文化センター企画協力講座に関して/知求アカデミーの新規講座に関して 他 審議事項:第35回大会に関して/ブリヂストン美術館秋期連続講演会に関して/スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会15周年記念シンポジウム共催に関して 他 |
地中海学会大会 地中海トーキング要旨 島の魅惑 ──ああ,松島や── パネリスト:浅野和生/佐藤弘夫/芳賀京子/和栗珠里/司会:安發和彰 |
|
地中海世界への誘いであるトーキングの今回のテーマは,大会準備委員会において,仙台の伊達家に縁りのある松島を中心とした「島の魅惑──ああ,松島や」とされた。当初は,景観・紀行文・リゾートへの展開等を念頭において「島々への旅」を内容とするつもりであった。とはいえ,松島についてのパネリストを日本思想史の佐藤弘夫氏(東北大学)に依頼するにあたって,佐藤氏が,とくに中世の松島が宗教的聖地として如何に成立し,変貌していったのかを実証的に追及されてきたところに注目して,そこにポイントをおく方向に舵をきった。結局は,「霊場の聖地,宗教的拠点としての歴史を誇り,景勝の地としても広く知られた松島をはじめとして,地中海の三つの島をとりあげ,本土との関係,その歴史,民族,建築,美術などの面から,古来,人々の興味をひきつけてやまない島々の魅力を語り合うこと」を趣旨として,パネリストの方々に報告を依頼した。報告および論議のキーワードに景勝・霊場・宗教と建築・美術をあげた。 当日は,司会者である私から簡単に上記の趣旨を説明したうえで,松島をめぐる佐藤弘夫氏の報告を皮切りとした。佐藤氏は広く日本の霊場や人々の死生観に深い関心を寄せる立場から,松島の歴史をふりかえり,とくに「地先の島」雄島に注目して,そこが,13世紀から納骨の霊場として尊ばれるようになった経緯を,近年の発掘の成果もまじえ,板碑(死者供養のための石碑)の遺例をあげながら解説した。この雄島こそが,聖地松島のおこりであり,もとは松林もなく,納骨の人骨や灰が地面を覆うところで,「此岸から霊のはなれる境界」「彼岸へのツール」「救済を待つ島」であったとした件りは,私たちの歴史的想像力を大いに刺激した。 地中海からは,まず,大小260の島々を有する松島同様,陸地近くのラグーナのなかに数多くの島々が点在するヴェネツィアについて,近世ヴェネツィア史を専門とする和栗珠里氏(桃山学院大学)が報告した。そもそも118の島から成る本島の成り立ちからはじめ,ラグーナ内の主要な島々を紹介しながら,渡し船でネットワークをつないだ「島のヴェネツィア」を解説する内容であった。聖マルコの遺体を収容した本島,墓地としてのサン・ミケーレ島,検疫と隔離病院の島々等,全島で相互に機能しあうヴェネツィアの姿が浮かびあがった。 つづいて,古代ギリシア美術史が専門で,ロドス島の |
古代彫刻に関する著書のある芳賀京子氏(東北大学)がエーゲ海,キュクラデス諸島のデロスに関して報告した。女神レトがアポロンを産んだとされるギリシア神話の聖地が,ヘレニズム時代にいたって宗教・芸術・商業の中心地として栄えた歴史を美術作品の紹介も含めて明らかにした。古来の景観,ギリシア本土からの参拝者をまねいた神域,浄祓されて墓が撤去された経緯と順次触れていくなかで,この島に独特の聖性の所在が明瞭にされていった。現在も観光施設に侵されない岩がちの島の姿,夕陽のなかで居並ぶ大型獅子石像を抱く島影をとらえた美しい写真の数々も印象に彩かだった。 最後に浅野和生氏(愛知教育大学)が,トルコはリキア地方のゲミレル島に関する報告をした。ビザンティン美術史を専門とする浅野氏は,10年以上,現地で中世キリスト教の聖堂建築やそのモザイク装飾の調査・発掘に関わってきた経験をもとに,7世紀に崩壊したこの島の文化について,聖ニコラオス信仰発生の契機を探り,四つの聖堂を中心とした島の姿の再現を試みた。さらにトルコ本土との関係において,この地先の島が航海の安全を祈願するモニュメントとなっていたという,島の存在の精神性に踏み込む所見を示した。本土から臨むゲミレル島の横長のシルエットは,端正で凛とした威厳をそなえ,小松崎浜から見る雄島の姿と重なるようであった。 報告後に,会場から質問を受けたなかでの論議においては,「日本三景」たる松島の景勝に関して,多島海の奇岩,異岩が呈する絶景が,異境・彼岸の入口,仏を観ずることを可能にするトポスの必須の条件であったにちがいないと思われた。その点では,地中海でも,信仰を異にするとはいえ,聖なる島々は,絶景のなかにそれぞれの死後の不可視の世界が混じり合う魅惑を湛えているのだとあらためて感じられた。 報告者各氏は,地中海の島々と松島との関連を探りながら,宗教性を中心に,歴史・風景・遺跡・美術等について具体的に触れながら報告をまとめ論議をすすめていた。今回のトーキングが充実して楽しかったのは,報告者各氏の高い見識のたまものだったと思う。共感を寄せて下さった聴衆の皆様,企画の円滑な進行に尽力下さった,飛ヶ谷潤一郎氏(東北大学)をはじめとする多数の方々にも,司会者として御礼申し上げます。 (安發和彰記) |
春期連続講演会「地中海世界における異文化の交流と衝突」講演要旨 西洋化するイスラーム世界,イスラームを抱え込むヨーロッパ ──近現代における展開── 飯塚 正人 |
|
7世紀前半にイスラームが生まれ,いわゆる「大征服」によって地中海沿岸に進出して以来,ヨーロッパとイスラーム世界は西でも東でも衝突と交流を繰り返してきた。イベリア半島やシチリア,あるいは十字軍の占領した聖地エルサレムをめぐる攻防が,結果として,17世紀の科学革命につながる「12世紀ルネサンス」(西欧知識人によるアラビア語科学・哲学文献,同ギリシア語文献のラテン語への大翻訳運動)を呼び起こしたことは,いまや周知の史実となっている。地中海世界のどこかで両者が戦っているときでも,東西南北を結ぶ商業活動はまた別のルートを取って継続され,交流がやむことはなかった。そして両者間の軍事バランスは,15世紀後半にオスマン帝国がビザンツ帝国を滅ぼす一方で,イベリア半島のレコンキスタが完了したことに象徴されるように,18世紀まではおおむね互角だったと見ることができる。 ところが19世紀に入ると,1798年のナポレオンによるエジプト遠征,1830年に始まるフランスのアルジェリア侵攻を経て,すでに産業革命を成し遂げていた西欧諸国の優位は誰の目にも明らかになった。この事態を受けて,エジプトのムハンマド・アリー朝は軍の西洋化をはじめとする富国強兵政策を推進。印刷所やアレクサンドリア・マルセイユ間の定期蒸気船航路,果てはスエズ運河まで開設したものの,1882年以降イギリスに軍事占領されてしまう。一方,オスマン帝国も遅まきながら軍の西洋化に取り組み,1876年にはヨーロッパをまねてアジア最初の近代憲法を制定しながら,第一次世界大戦に敗れて滅亡。新たに建国されたトルコ共和国はアラビア文字もトルコ帽も捨てて,ラテン文字とシルクハット,それに西洋式の学校教育を導入するなど,猛然と西洋化への道を突き進むこととなった。 こうした西洋化路線には当初から「イスラームの教えに反するのではないか」との疑念がつきまとい,時に改革の障害ともなったが,やがて一群の改革思想家が現れ,イスラームと近代西洋の価値観にそれほど大きな違いはない,西洋の科学技術も元はと言えばイスラーム世界から輸入されたもので,ムスリムは失ったものを自らの手で取り戻さなければならないなどと主張して,西洋化を盲目的に否定しない態度こそ逆にイスラーム的に正しいという思想を広めていく。その結果,イスラーム世界では例外なく西洋化が進み,今日では洋装も洋食も洋 |
風建築も,洋風音楽や絵画でさえ珍しくはなくなった。 もっとも,特に女性の服装をめぐって西洋化の「行き過ぎ」を警戒する声,強い反発が一貫して存在してきたことも事実である。ヨーロッパがイスラーム文明の後進性の象徴としてムスリム女性のヴェールを厳しく批判したことが,逆に男たちの警戒心を煽ることになった。ヨーロッパは女性の西洋化を通じてムスリムの社会と文化を破壊するつもりではあるまいか? そうならないよう,ムスリム女性は西洋とは異なるイスラーム固有の価値観に従わなくてはならない……多くのムスリムにとって,ヨーロッパの女性が貞操観念とは無縁の存在に見えたこともこうした思いを強くさせた要因だったろう。 かくて西洋化を免れ,期せずしてイスラーム固有の価値観を象徴する役割を担わされた女性のヴェールは,1980年代以降,ヨーロッパが大量のムスリム移民を抱え込むようになると,否応なく注目を集めていく。第二次世界大戦で多くの若年労働者を失った西欧諸国は,高度経済成長期を迎えた1950年代以降,イスラーム世界から組織的に出稼ぎを受け入れたが,1973年のオイルショックで深刻な不況に陥ると,不要となった出稼ぎ労働者に帰国か移民かの選択を迫った。このとき多くのムスリムは移民の道を選び,故国の家族を呼び寄せる。こうして突如,西欧の街角にヴェールをつけた女性が現れ,ヨーロッパのイスラームが可視化することとなったのである。 とはいえ,各々の民族が固有の性質を持ち,そこに優劣はないと考える「多文化主義」のイギリスやオランダがムスリム女性のヴェールを問題視することはなかった。けれども,人間は姿や習慣の違いを超えて本質的に同じと考え,移民に同化と適応を求める「普遍主義」のフランスでは,フランス文化に同化しないムスリムが問題とならざるを得ない。加えて女性のヴェール(スカーフ)がイスラームの象徴であるとすれば,公立学校にヴェール着用で登校することは,共和国の「世俗主義」原則への挑戦にもなるだろう。1989年以来今日までフランスやベルギーを騒がせ続けているスカーフ問題は,ホスト国側に特有のこうした事情が生んだものと言える。 他方で1980年代以降は,ムスリム「第二世代」「第三世代」の就職難と彼らに対する差別が顕在化した。相互不干渉の原則を貫いてムスリムと共存してきたヨーロッパが今後どこへ向かうのか。行く先はまだ霧の中である。 |
「地中海宮」のアール・デコ 三田村 哲哉 |
|
建築や美術に関心がある向きなら,「アール・デコ」という言葉を一度は耳にしているに違いない。19世紀末に流行したアール・ヌーヴォーに続く新造形が,第一次世界大戦後,建築,絵画,彫刻のみならず装飾,家具,鉄工,陶芸,硝子,宝飾,服飾,装丁など,実に幅広いジャンルの作品に見られるようになる。我々はこの新しい芸術全体を捉えて「アール・デコ」と呼んでいる。ところでアール・デコの建築といえば,ニューヨークのクライスラー・タワーなど,斬新で煌びやかな作品が思い浮かぶかもしれない。とはいえ,モダニズム建築を中心に展開されてきた近代建築史では,このような装飾建築は1960年代半ばまで排除される傾向にあった。その後,研究が進み,ベルギー,イギリス,アメリカ,カナダといった先進国はもとより,北アフリカや東南アジアや東アジアの保護領,さらには南米諸国,ニュージーランド,南アフリカに至るまで,世界の主要都市でアール・デコの建築が次々に「発見」されている。新たな総合芸術と関連産業の世界覇権を目論み,フランスが1925年にパリで開催した現代装飾美術・工芸美術国際博覧会(アール・デコ博)の成果が,こうして今,世界各地で明らかにされつつある。 一方,フランス国内への波及は限定的で,パリの一部の映画館や集合住宅,および後続の博覧会の展示館などにとどまると解釈されてきた。しかし,戦間期のフランスで発行された主な建築専門誌を繙いてみると,アール・デコの建築がフランス全土に多数建設されたことが確認できるばかりか,これまで詳細なフランス近代建築史にも全く登場しなかった優れた作品が認められるのである。また近年,地方の美術館や自治体などが,文化活動や観光事業を目的として地道に蓄積してきた研究の成果を,地域独自の出版物や展覧会やブックレットの形で次々に発表している。 1929年1月1日,南仏コート・ダジュールのリゾート地ニースの美しい海岸線の中程,プロムナード・デ・ザングレの中心に建設されたカジノ「地中海宮 Palais de la Méditerranée」も見過ごされた建築の一つである。計画案を見ると,その壮大さに圧倒される。ニースにはすでに二つのカジノがあったが,アメリカ鉄道王の子息フランク・ジェイ・グールド(1877~1956)が出資して,新たなカジノが建設されることになった。地元の大建築家ダルマス親子(1865~1938,1892~1950) |
は,「地中海宮」の名を裏切ることなく,地中海随一の宮殿を目指して贅の限りを尽くした計画案を描いた。社交場であるカジノは,賭博場もさることながら,広い祝宴場を中心として,音楽ホールや劇場,レストランなどを備えるのが一般的であった。「地中海宮」はこれらに屋上庭園と6階建ての近代的なホテルが加わり,地下には,プロムナード・デ・ザングレの下を潜って砂浜につながる温水浴場と冷水浴場,そして蒸気によるローマ風呂が描かれたのである。 有閑階級の快楽を追求したこのダルマス親子のプランには,フランス建築の伝統を継承しつつも最新の流行を取り入れるアール・デコが採用された。中央のホールから「バカラの間」までを満すアール・デコの中でも,その特徴を最もよく表しているのはプロムナード・デ・ザングレに面したファサードである。それは全体を建築家シャルル・ガルニエ(1825~1898)によるパリのオペラ座に倣い,他方で破風やオーダー,鉄工や硝子などの部分に,当時の新たな造形を取り入れたものであった。実現したのはホテルと地下を除いた部分にとどまったものの,ある建築専門誌は,1930年から翌年にかけて10回にも及ぶ異例の特集記事を組み,同宮を数少ない「真の近代建築」と高く評価した。また作家ジュール・ロマン(1885~1972)は,大作『善意の人々』の中で,「戦間期のフランスは大型客船『ノルマンディー号』と『地中海宮』という二つの傑作を生み出した」とさえ述べている。「地中海宮」は全欧屈指のカジノとしてその名を知られるようになり,高名な賭博師のみならず,世界の億万長者や各国の王侯貴族がお忍びで通う,享楽のための建築の頂点に位置付けられたのである。 翻って今日,フランスではその役を終えたカジノがコンベンションセンターや市民の文化施設などに転用され,各都市の中核施設として再生されている。この「地中海宮」はさまざまな議論の末,立面のみを保存して良しとする「ファサード主義」の餌食となり,2004年に豪華ホテルとして再建された。アール・デコの作品は周囲の古建築とも調和するという,モダニズム建築にはない優れた特徴を有している。そのため人知れず存在していることもしばしばある。フランス内外の各都市に埋もれた傑作を丹念に洗い出す作業が新たな解釈を生む日が,いずれ訪れるかもしれない。 |
リカーソリ通り23番 赤松 加寿江 |
|
留学していた頃の住いが気になって,昨年夏,久しぶりに訪れてみた。大聖堂からサンマルコ広場に伸びるリカーソリ通りの中程,フィレンツェで一番おいしいといわれる,シチリア人がやっているジェラート屋のすぐそばである。私はパラッツォの1階に住み,2階には大家さんの70歳位のシニョーラが一人で住んでいた。 留学生活も終わりに近づいた6月,その大家さんが突然亡くなった。旅行先のナポリで死んだという知らせとともに,初めて見る息子達が次々に家にやってきた。「君も次のところを探してくれ。支払いは滞ってないだろうね? その自転車もちゃんと持っていってくれ。」事故処理や葬儀準備の慌ただしさだけではない語気が伝わってきた。その夕方,声を荒げた言い合いが天井越しに聞こえてきた。はっきり聞き取れなくても,意味の想像はついた。 シニョーラは上品で優しく,道で会えば長々と話をしてくれた。しかし,月1度家賃を支払いに部屋を訪ねる時はえらく緊張したのを覚えている。1階から2階へあがる階段は,塔状住宅のような狭い階段ではなく,幅広で緩やかだった。質のいい絨毯が敷かれ,広い踊り場には彫刻が飾られていた。2階の入口には,大きな木の扉が閉じられ,毎回部屋の威厳に緊張しながら「シニョーラ,シニョーラ」と声をかけて支払いをしたものだった。室内は暗く,高価そうな家具が所狭しとあるものの,何があるのかさっぱり見えなかった。畏怖を感じる雰囲気を背景に話すシニョーラの存在は,私の中でイタリアの没落貴族婦人そのものだった。 その突然の死,しかも遺体が見つからないという事故状況,相続にもめる息子達,ドラマのように立て続けにおこる出来事は,私にも少なからず影響を与えた。シニョーラが「私は乗らないから使って」と貸してくれていた自転車を返し,予定外に早くその家を去ることになった。こんな状況でシニョーラにお別れするとは思ってもなく,最後のありがとうを伝えられなかったのが悔やまれた。息子達があのパラッツォをどうするつもりなのかも気になっていた。その後,数年してから,ファサードにはレジデンスホテルの看板がかけられていた。 あれから10年経ったキリの良さを記念して,受付と書かれたカンパネッロを押してみることにした。かつて毎日出入りしたその扉が,ジーと鳴って開く。期待して |
いたのは,中庭の緑に向かって薄暗く伸びる廊下。しかし,目の前に現れたのは,クリーム色に塗られた壁に,明るい照明。書画風のアートポスターがかけられたモダンなインテリアである。改装の衝撃に目を泳がせていると,受付からボンジョルノと東洋人女性が現れ,「ご予約の方ですか?」と日本語がかえってきた。 その人は,相続に揉めた息子達からこの建物を丸ごと一棟購入したという日本人オーナー。工事に数年かけてようやくオープンさせたという苦労話を聞きながら,改装されたスペースを見て回る。高い天井だった1階は,鉄骨の螺旋階段とロフトが付け加えられ,ロフトは執務スペースとなっている。かつての摩耗しきったテラコッタの床は張替えられ,洗面器程度だったバスタブは,ガラス張りのバスルームへと生まれ変わり,こんなところに住みたいと思わせるお洒落な客室に生まれ変わっている。 イタリアの建築家と職人ならではの改装の妙技にうなずきつつ,「今度はここにお客として泊まりたいです」などといいながら,そのときどんな風にシニョーラを思い出すかと考えると,なんともいえなくなった。 それにしても,古いパラッツォやヴィラをホテルとして転用できる事例はうらやましい。ホテルは多くの人が空間体験をできるという点からも,歴史的建築物を利活用する上で好ましい展開のひとつだと思う。日本では,比較的規模の大きい歴史的住宅があっても,用途地域制限によって,住居をホテル等に転用できないことが多い。住居専用地域でのホテル営業は認められていないからだ。私の住む鎌倉でも,歴史的な別荘住宅の多くは解体,土地分譲され続けて,数はどんどん減ってきた。 7月の地中海学会研究会において会場として使われた旧里見弴邸も歴史的な住宅のひとつだ。築85年を迎える洋館と茅葺和室が,大規模な改装もなく住み継がれてきた。公開を始めて2年たったものの,歴史的な住宅を残しながら,活用していく課題は山積みだ。アイデアは色々あるとして時代の記憶を残す空間を使っていくには,法整備のみならず,ホテルに改装できるくらい財力も必要だ。 |
自著を語る64 L. B. アルベルティ著,池上俊一・徳橋曜訳『家 族 論』 講談社 2010年7月 558頁 3,465円(税込) 徳橋 曜 |
|
レオン・バッティスタ・アルベルティの『家族論』を池上俊一氏との共訳で,去る7月に上梓した。15世紀の人文主義者アルベルティの名は,日本でも歴史・美術・建築・文学と様々な分野で知られており,『絵画論』や『建築論』が邦訳されている。『家族論』I libri della famigliaも,家族史・社会史・教育史の研究者には夙に知られており,部分的にはしばしば引用されるし,第一書の抄訳もあった。しかし,これまで全訳は存在しなかったのだ。実のところ筆者自身,今回の仕事をするまでは,斜め読みしながら必要な部分を摘み喰い的に利用した(例えば,商人文化に関連して「商人の指は常にインクで汚れているべき」という第三書の有名なフレーズを引用するのは,殆ど「お約束」である)程度で,最初から最後まできちんと読み通したことはなかった。 翻訳は延べ10年以上にわたる長い仕事だった。原文には解りづらい部分も多々あり,底本としたイタリア語版以外にも,複数の英語版やイタリア語版を参照した。しかも,面白い内容ではあるが,しばしば登場人物の長広舌が続く。そんな場合は3ページも訳すとうんざりしてきて,しばらく投げ出していた(今更ながら申し訳ない)。ともあれ何とか粗訳をし,徐々にまともな日本語に仕上げていったのだが,共訳ならではの苦労もあった。俗語の対話形式なので固い文章語は使わない,というのが池上氏との合意であり,二人で相談して各登場人物の口調に特徴を与えた。リオナルドは才走ったちょっと生意気な若者,アドヴァルドは良識的で世間慣れした既婚の中年男性といった具合である(原文ではそれほどの特徴がない)。しかし,訳者それぞれの文体や口調の癖が滲み出るのは避けられない。特に全巻を通じて良く喋るリオナルドと,第二書以外の各書に登場するアドヴァルドについては,口調のすり合わせが必要だった。 しかし,そういう苦心をしつつも,対話形式の翻訳は芝居を作っているような楽しさがあって,個性的な登場人物達にどんな風に掛け合いをさせるか,どんな口調で喋らせようかといろいろ考えた。とりたてて真似たわけではないが,イメージの土台になったものの一つは,『吾輩は猫である』で苦沙弥先生他の面々が展開する世の雑事についての議論,もう一つはシェイクスピアの戯曲,特に昔読んだ福田恆存訳の『ヘンリ4世』や『お気に召すまま』等の台詞の掛け合いであった。東西の文豪に肩を並べようとはさらさら思わないが,文中での掛け合い |
を自然なものに感じてもらえたら嬉しい。 さて同書の解説でも書いたが,『家族論』は様々な古典を論拠とする。『家族論』が書かれた1430年代,活版印刷による書物はまだ存在しない。アルベルティは古典を学ぶなかで得た知識や写本を参考にしたのだろう。手軽に参照できるように,古典の要点を抽出した書物もあったらしいが,限られた文献を丹念に読み込むというのは,溢れかえる文献を追うのに精一杯な身としては羨ましい。だが労力を要したのが,その典拠の確認だった。英語版の一つに付された典拠注を水先案内として,内容を照合すると,ときに引用が典拠元の内容に一致しない。作者が曖昧な記憶に頼ったためか,参照した写本自体に誤りがあったからか,典拠に厳密たらんとする意識がなかったのか。例えば,「クセノポンによれば」と,詩人シモニデスが僭主ヒエロンに対して語った教育論が直接話法で引用されているが,クセノポン『ヒエロン』の該当箇所は,同様の表現ではあっても,臣民に対する支配者の態度を論じるものだ。あるいは,ウェスパシアヌス帝の言として挙げられたものをスエトニウスで確認すると,実はその吝嗇な皇帝を罵った農夫の言葉だったりする。 こんな具合で,典拠を確認しないとどうも危うい。だが,想定される一般読者に対して,作者の誤解や記述の齟齬を詳細に指摘するべきか,そもそも典拠注自体が必要かという議論もあった。齟齬を周知のこととして,典拠を示すに止める(参考にしたどの版にも,明白な誤り以外の齟齬の指摘はない)ことも考えた。だが結局,専門家の利用にも耐えるものにするという結論を認めてもらい,典拠注(編集者曰く「専門家向けの言い訳」)を付して,内容の齟齬や作者の誤解も指摘した。幸いアルベルティの依拠した古典の多くに邦訳があり,それが典拠の照合作業に大いに役立った。さらに有難かったのは,アルベルティが依拠している総ての古典の原文や英語訳が,インターネットで閲覧できたことで,古典学者の情熱と努力に脱帽した。だらだらと長期にわたった翻訳作業を正当化する気はないが,何が幸いするか判らない。10年前なら照合作業は遥かに苦労だったろう。情報化の進展に感謝である。 こうして世に出せた『家族論』である。多くの人の役に立てば幸いだ。勿論,筆者自身大いに活用したい。 |
|
地中海世界と植物12
アッケシソウ/加藤 玄 |
|
ここ数年,フランスの湿地の歴史に興味を持ち,建築史の専門家らと「沼地研究会」を組織した。その現地調査に先立つ9月初旬の日曜日,日頃の運動不足の解消も兼ねて,カマルグ湿原をサイクリングしようと思い立った。湿原の西南端に位置する町サント・マリー・ド・ラ・メールで自転車を借り,意気揚々と出発。走り始めてしばらくは,有名な白馬,雄牛,ピンクフラミンゴを見つけてはシャッターを切った。しかし,南仏の日差しが容赦なく照りつけ,未舗装の放牧路と堅いサドルのせいで尻が痛くなり,沼沢地ならではの蚊の大群にも悩まされ,早くも一時間ほどで音を上げた。同じくサイクリング中の恰幅の良い年配女性に追い越された屈辱感も加わり,這々の体で退散することにした。 初めて見たカマルグの印象は,「散文的」の一言に尽きる。かのアルフォンス・ドーデも「カマルグの岸べは,たいがい,乾燥,不毛でさびれている」(桜田佐訳『風車小屋だより』岩波文庫所収)と述べていたのではなかったか。翌日,「沼地研究会」のメンバーと合流し,今度は車で東南端の町サラン・ド・ジローに向かった。前日とはうってかわって,ヴァカレス湖岸に沿ったドライブは快適であった。冷房の効いた車内からはカマルグの風景が心なしか優しく見えた。「カマルグで一番景色のよいのはヴァカレスである。(中略)ヴァカレスの湖は,やや高く柔らかいびろうどの草で真緑のその岸の上に珍しく美しい花畑を延べ広げている」。いみじくもドーデが書いている。 高さ数十センチメートルの植物によって覆われたカマルグ南部の典型的な景観は「サンスイール」と呼ばれ |
る。土壌に多量の塩分が含まれているため,通常の樹木は生育できない。ある種の植物だけが,葉肉部に蓄積した雨水や露を循環させ,細胞内の塩分濃度を下げることでこの環境に適応したという。表紙写真のアッケシソウ(仏名サリコルヌ)はその代表的な塩生植物である。ドーデが「柔らかいびろうどの草」と呼んだのもこの草だ。荒漠としたカマルグの風景に,穏やかな優しさを添えるアッケシソウは,匍匐性一年草で密集した茂みを形成し,サンスイールに夏には緑,秋からは赤みを帯びた彩りを加える。ヨーロッパだけではなく,実は日本各地にも生育していて,和名は発見地である北海道東部の厚岸町牡蠣島にちなむ。カマルグでは食材としても知られ,一度熱湯にくぐらせてサラダにすることが多い。春に収穫される茎はシャキシャキとした歯ごたえがあり,塩味がする。 アッケシソウが繁茂していたカマルグで大規模な治水事業が行われたのは,19世紀中頃のナポレオン3世の統治下である。洪水を防ぐため,ローヌ川沿いや海岸線に堤防が建設され,ローヌ川から淡水を供給する施設が整えられた。こうした人工給水は,今日の稲作を代表とするカマルグ地方の農業,牛や馬の牧畜,鳥類の生息には不可欠である。ナポレオン3世は,中国を真似てカマルグの景観保護を構想したらしい。そう教えてくれたのは,レンタル自転車屋の店員であった。彼の本業は鳥類の研究で,週末にカマルグ湿原中を歩き回っては,鳥類の観察に勤しむのだとか。たかだか数時間のサイクリングごときでへこたれていては,沼地のフィールドワーカーには到底なれないのだと思い知った。 |