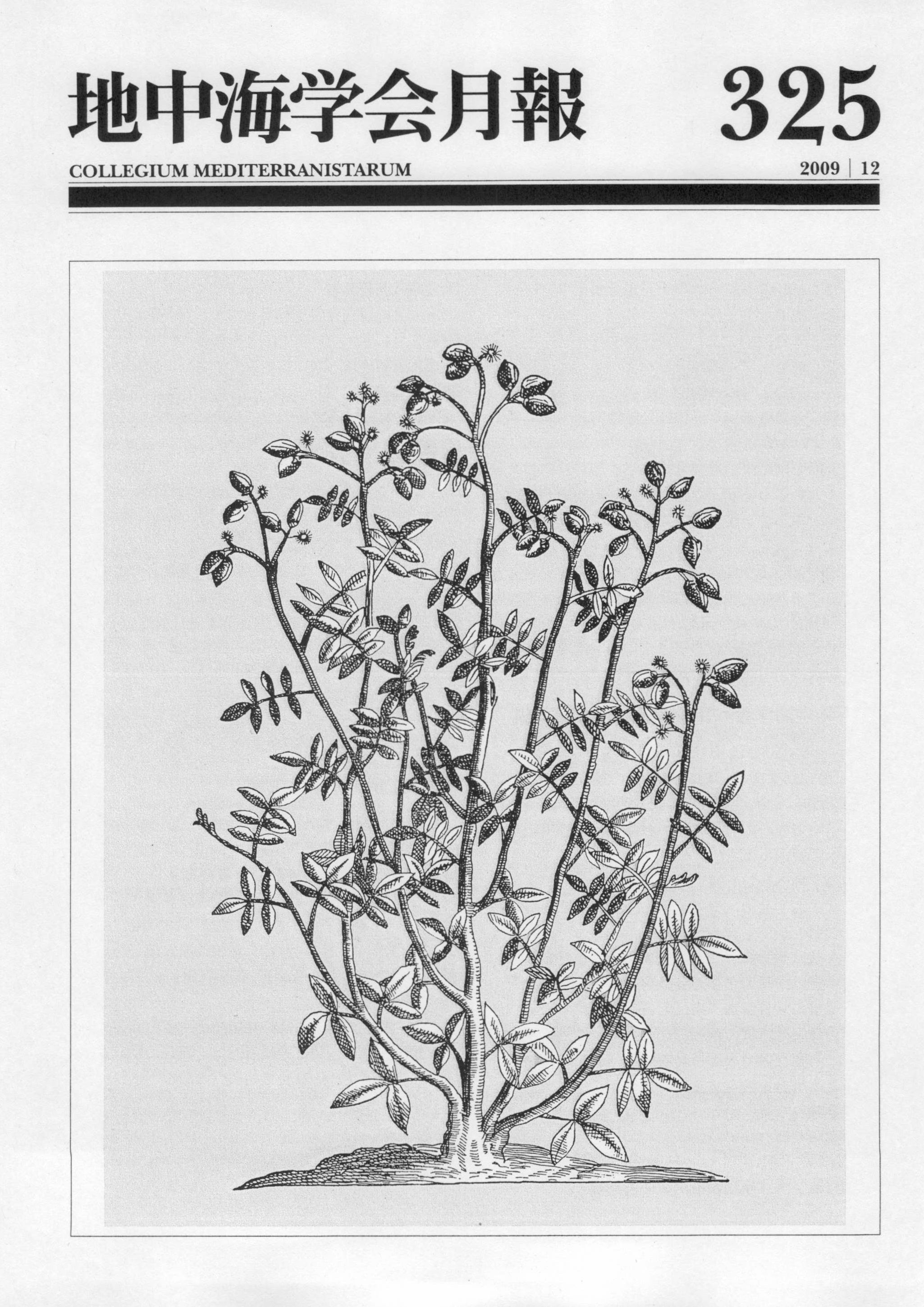|
*2月研究会 下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。 テーマ:パレストリーナのナイルモザイク 発表者:田原 文子氏 日 時:2月20日(土)午後2時より 会 場:東京大学本郷キャンパス法文1号館3階315教室 参加費:会員は無料,一般は500円 紀元前2世紀末頃制作されたイタリア,パレストリーナのナイルモザイクは,制作年代やその建造物の機能に関して定説が定まらないこと等から,発見当初よりフォルトゥナやイシス信仰の宗教画,地誌的地図といった様々なテーマの解釈がなされてきた。モザイクの主題を考察する上での諸問題を整理すると共に,古典史料のナイル河に関する言及から,モザイクに描かれたナイル河の氾濫風景にどのような解釈が可能であるかを考察していきたい。 *「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集 地中海学会では第15回「地中海学会ヘレンド賞」(第14回受賞者:畑浩一郎氏)の候補者を下記の通り募集します。授賞式は第34回大会において行なう予定です。応募を希望される方は申請用紙を事務局へご請求ください。 地中海学会ヘレンド賞 一,地中海学会は,その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。 二,本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は,原則として会員を対象とする。 三,本賞の受賞者は,常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し,その業績審査に必要な選考小委員会を設け,その審議をうけて受賞者を決定する。 募集要項 自薦他薦を問わない。 受付期間:2010年1月8日(金)〜2月12日(金) 応募用紙:学会規定の用紙を使用する。 |
*第34回地中海学会大会 第34回地中海学会大会を2010年6月19日,20日(土,日)の二日間,東北大学において開催します。プログラムは決まり次第,お知らせします。 大会研究発表募集 本大会の研究発表を募集します。発表を希望する方は2月12日(金)までに発表概要(1,000字以内)を添えて事務局へお申し込みください。発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。採用は常任委員会における審査の上で決定します。 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には月報324号(11月)に同封して振込用紙をお送りしました。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方,学会発行の領収証を必要とされる方は,お手数ですが,事務局までご連絡ください。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行 九段支店 普通 957742 三井住友銀行 麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2010年度会費からの適用分です)。 会費口座引落:会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度入会された方には「口座振替依頼書」を月報324号に同封してお送り致しました。手続きの締め切りは2月23日(火)です。ご協力をお願いいたします。 なお,すでに自動引落の登録をされている方で,引落用の口座を変更ご希望の方は,新たに手続きが必要となります。用紙を事務局へご請求下さい。 事務局冬期休業期間: 12月26日(土)〜1月7日(木) |
|
秋期連続講演会「地中海の光」講演要旨 クロード・ロランと戸外制作 ──ローマが「風景」になったとき── 小針 由紀隆 |
|
「理想風景画の確立者」──芸術家クロード・ロランを評する上で,これはもっとも適切な言い方であろう。1604/05年にロレーヌ地方の小村シャマーニュに生まれ,若くしてローマに移ったクロードは,短期間のうちに風景画家として頭角を現し,1630年代後半にはローマ教皇やスペイン国王など,特権階級のパトロンを相次いで獲得していった。M.キットスンによれば,現存するクロード作品は,油彩画250点,素描1,300点(『真実の書』を含む),版画44点で,これらの作品の編年的考察は,クロードによる理想風景画の様式確立と展開を浮かび上がらせる。 しかし,最近30年の欧米における風景画研究は,クロード初期の制作活動にあらためて光を投げかけている。その研究対象となっているのは,18世紀後半からローマとその近郊で爆発的に急増した油彩による風景スケッチである。この美術現象が起こった真の理由についてはうまく説明できないが,ヨーロッパの各地からローマにやってきた若い画家たちは,申し合わせたようにこの技法に取り組んでいた。注目されるのは,油彩による戸外制作の伝統の最先端にクロード・ロランが立っていたことで,ここには理想風景画の担い手とは異なる,もうひとつのクロード像がみえている。 この点について,もう少し注釈を加えておこう。1620年代後半からローマに滞在したザントラルトは,『ドイツのアカデミー』の中で次のように述べている。クロードは野であちこち観察し,すばやく絵具を調合すると家に引き返し,手がけていた作品に調合した絵具を塗るのだった。ところがティヴォリの滝のある岩場で,絵筆を手にしたザントラルトと出会った。「そこで彼(クロード)は写生をしている私を見つけ,私が自然そのものから多くの絵を描き,想像からは何もうみださないことを知った。彼は大いに喜び,同じこの手法を好んで用いるようになった。」つまり,クロードはザントラルトから,戸外での油彩スケッチの技法を教わり,その技法を繰り返し用いた,というのである。 この記述の信憑性を考えるにあたって最も大きな問題となるのは,クロードによる油彩風景スケッチの作例が一点も見つかっていない点である。文献上は17世紀のイタリア,特にローマとその周辺で,油彩風景スケッチが実践されていたことになるのだが,実際の作例は提示 |
できない情況にある。画家の残した数少ないスケッチがすべて失われてしまった,あるいは現存していても保存状態が劣悪なため,特定の画家に帰属しえないなど,その理由はいくつか考えられる。しかし,自然からの油彩スケッチが実践されていたという見方は,いくつかの傍証を吟味,検討する研究者たちから支持されていて,その見方を覆すような論拠はどこからも提示されていないのである。 クロードの自然研究に傾けた情熱には並々ならぬものがあった。現存するクロードの作品には,自然から直接描いた素描を容易にいくつも探し出すことができる。紙に褐色ウォッシュや黒チョークで描いた自由で粉飾のない素描は,自然の多様な様態に対するクロードの素直な情動の反応を映し出すとともに,光の効果,量塊のバランス,明暗の配分などへの画家の旺盛な研究心を伝えている。クロードは油彩スケッチに着手していたらしいが,自然を研究するには淡彩の素描がよいと考えていたのかもしれない。油彩の風景スケッチが本格的に実践されるようになるには,クロードの没した一世紀後,すなわちヴァランシエンヌが登場する1780年代を待たねばならなかった。 油彩風景スケッチが実践されるカンパーニャの美を発見したのは,16世紀後半以降,ローマにやってきた外国人,特に北方の画家たちだった。ローマから数十キロ離れたティヴォリ,ズビアコ,フラスカーティ,ガステル・ガンドルフォ,ネミなどは,画家たちにとって何時でも利用できるモティーフの宝庫であった。彼らと同様クロードも,古代の遺跡や芸術遺産,ピクチャレスクな光景などを,自然の中から選択・描写するのだった。 クロード・ロランの名声は,理想風景画の確立者,規範的風景画の創出者として,没後200年以上衰えることがなかったが,その一方で彼は油彩による戸外制作の実践者としても先駆的な役割をはたしていた。クロードは自然に対する実直な反応を,アトリエにおける完成作に誰よりも無理なく注ぎ込めた画家であり,彼の中では手控え的な作品と公的な作品とが幸福に結びついていた。こうした天賦の才がなかったとしたら,ローマ内外の自然から理想風景画を立ち上げる偉業を達成できなかったに違いない。 |
|
研究会要旨
イラン・テヘラーンに建設された ガージャール朝(1796〜1925年)の宮殿と離宮 ソレマニエ 貴実也 10月4日/東京大学本郷キャンパス |
|
ガージャール朝期の宮殿を紹介する前に先ず,18から19世紀のイランとイランを取り巻く社会・政治背景を整理し,宮殿の主である王達の思想や思惑を整理する。 イスラーム教シーア派的血脈を持ち,歴史都市イスファハーンを首都とした,サファヴィー朝(1501〜1736年)と異なり,18世紀末にガージャール朝を設立させたガージャール族は,中央アジアを出身地としたトルクマン系遊牧民族であった。彼らには天下統一を図るため,イラン(ペルシア)の王としての正当性を示す必要があった。そこで持ち出されたのが,古代ペルシア帝国アケメネス朝(紀元前550〜前333年)とサーサーン朝(紀元226〜651年)への憧憬,古代(ペルシア)復興的思想であった。 更に対外関係に目を向けると,サファヴィー朝期までのイランはイスラーム勢力オスマン朝を意識し,イスラーム教国家としての立場保持に努め,これを前面に出し国政の強化に努めた。しかし19世紀に入るとオスマン朝は弱体化し,替わって西欧列強がアジア諸国の植民地化に乗り出した。イランも植民地化こそ免れたものの,数多くの不平等条約を結ばされた。そんな中,第4代君主ナーセロッディーン・シャーは3度も西欧諸国を訪れ,積極的にその制度や技術を導入した。 この様に18世紀までのイラン・イスラーム的思想に19世紀以降,イスラーム以前のイランつまりペルシアを重んじる,古典復興的思想が注入され,更に19世紀から20世紀初頭の世界情勢を反映して,西欧化とこれに伴う西欧的思想が,これらに加えられたのである。 では上記流れをふまえ,ガージャール朝の宮殿および郊外の離宮建築を数件紹介したいと思う。 エマーラーテ・タフテマルマル(大理石の玉座の宮殿) この建物は,宮殿街区に遺されている宮殿の中で最も古いものであり,その原形はサファヴィー朝の君主の宿泊施設であったとされている。しかし,宮殿として改築されたのは19世紀初期である。当時の様子をフランス政府派遣の使節に随行した画家フランダンと建築家コストの旅行記から確認することが出来る。描かれた挿絵より,本宮殿は中央にテラスを有し,左右に側室を配した3室構成であり,中央テラスには2本の高い石造ねじり柱が備えられていたことが確認できる。有蓋テラスはイランの諸建築に頻繁に登場する空間である。しかし,近世までイーワーンと呼ばれ,アーチやドーム天井で覆わ |
れた空間であった。石柱が平天井を支える建築はアケメネス朝のアパダナ宮殿までさかのぼるものである。 更に19世紀後半この宮殿を訪れ,王との謁見をはたしたフーリイェの旅行記には,次のように記されている。「……(本宮殿の)壁面には歴史上の王の姿が描かれ,金の枠で飾られている。……」壁面に描かれた歴代ペルシアの王の姿に囲まれて,玉座に座った本宮殿の主,第2代君主ファタリー・シャーは,この他サーサーン朝期のレリーフを自らの姿に造り替えていたことでも知られている。 シャムソル・エマーレ(太陽の宮殿,1867年) 宮殿街区に建つこの建物は,復古的傾向を受け継ぎながら,西欧化を勧めた第4代君主の宮殿である。本宮殿は3室構成の1階上部に,一対の塔を載せた地上5階建ての建築であり,全体の高さは35mに及ぶ。1階中央テラスには大理石製のねじり柱が設けられ,前述の宮殿と共通する要素がみられるが,上部テラスには,サファヴィー期の様式である,細い木製の柱が設けられている。更に上層部には2本の塔を連絡する通路状の諸室と当時の西欧化を象徴する時計塔が載せられている。 3室構成の部屋配置,木造の柱などの伝統的スタイルと,復古的な石柱テラス,そして時計塔が,「伝統」,「復古」と「西欧化」の奇妙な共存を象徴している。 ガスレ・フィールーゼ(1870年代) 最後にテヘラーン市外に建てられた,ナーセロッディーン・シャーの離宮を紹介する。この建物は,フランス帰りの建築家,モムタヘン・オル・ドーレが設計した初の洋館でもある。その建築的特徴は楕円形のプランと建物を360度取り囲む列柱テラスである。更にこれまでの切妻や寄棟のトタン屋根と異なる半球形トタン屋根もこの離宮の特徴であり,その後コラー・ファランギー (西洋帽)屋根として流行する。実はモムタヘン・オル・ドーレは自己の日記に「……数年後,一度も監督に訪れることなく私の設計した建物が建設されていた」と記している。つまり本宮殿は伝統的職人によって建設されたのである。そしてその後職人達の手によって洋館の要素が都市の中の建築と融合し,広まって行ったのである。 ガージャール朝の古典復興の動きは,ペルシア帝国と西欧古代の共存の歴史から,西欧と古代の共有を求める動きへと変化し,結果伝統スタイルに復古主義と西欧化を融合させた建築を生み出したのではないだろうか。 |
|
司教マインヴェルクの夢 太記 祐一 |
|
ドイツ北西部ノルトライン=ヴェストファーレン州に,パーダーボーンという人口14万人ほどの大学都市がある。この町にはかつてフランク王国の宮廷がおかれ,教皇レオ3世と,後に大帝と賞されることになるフランク王カールとの会見がもたれたことで知られる。中世の建築で現在に残るものとしては,11世紀初めの司教マインヴェルクによる初期ロマネスクの大聖堂が有名である。 このマインヴェルクのかかわった建築でバルトロメウス・カペレ(聖バルトロマイの礼拝堂)という作品がある。これは大聖堂の隣に立つ小さな建物でたいへん簡素な外見をしている。しかしこれは,かつてこの地に営まれていた神聖ローマ帝国オットー朝の宮廷礼拝堂として,1017年に建設されたものだった。 この建物は東側に半円形のアプシスが突き出している点を除けば,長方形の単純な形をしており,屋根も切妻のシンプルなものである。内部は6本の柱で支えられた交差ヴォールトがかかっている。装飾は建築彫刻以外残っていない。建築史においてこの作品は,ロマネスクの時代にスペインのカタルーニャ地方や南仏ルシヨン地方からヨーロッパ中に拡がった,広間式教会の流れで捉えられることが多い。しかし『マインヴェルク伝』によればこの作品は「ギリシアの工匠によって(per Grecos operarios)」完成されたそうである。 司教マインヴェルクは,神聖ローマ皇帝オットー三世やハインリヒ二世に助任司祭として使えたのち,パーダーボーンの司教となった。特にハインリヒ二世とは親交があったようで,司教への叙任には皇帝の後押しがあったといわれる。つまり彼は中心ではなかったかもしれないが,神聖ローマ帝国の中枢からそう遠くないところにいたにちがいない。このローマとは名ばかりの,ドイツに基盤をおく国には,地中海へのあこがれを抱く人々が当時,少なからずいたようである。彼らの目には,かつての偉大なローマ帝国が映っていたことだろう。もっともそれは単に文化的なものではなく,政治の現実的な要求から生じたものだったようではあるが。 例えば神聖ローマ皇帝オットー三世は古代のローマ帝国を夢見て,イタリア政策に深入りしていった。彼の母テオファヌはビザンツ皇帝ヨアンネス一世ジミスケスの姪といわれる。オットー三世自身もビザンツ皇女ゾエとの縁談が進んでいたそうである。しかしこれは皇帝本人 |
の急死によって実現しなかった。 ゾエはバシレイオス二世の姪にしてコンスタンティノス八世の娘である。25年ほど後にロマノス・アルギュロスが,彼女と結婚することによってビザンツの帝位に就くことに思いを巡らせるならば,二人が結婚できなかったことに運命の大いなるいたずらを感じずにはいられまい。 さてバルトロメウス・カペレに話を戻すことにする。以前よりこの建築のどこがギリシア的な,いいかえればビザンツ的な性格といえるのか議論となってきた。 交差ヴォールトが連続して並ぶ様は,ドームが連続して並ぶ教会建築の簡略版ではないかという意見もある。ドームが連続する教会とは,例えばヴェネツィアのサン・マルコであり,その手本となったコンスタンティヌポリスの聖使徒教会である。しかしこれら大作と比べるにはバルトロメウス・カペレはあまりに小さい。 柱が規則正しく並ぶのはコンスタンティヌポリスのバシリキ貯水池の様な地下貯水池に似ているという意見もある。建築の材料の使い方や構造の考え方といった点では,確かに傾聴すべき意見かもしれない。 要は,この作品には一目でビザンツ的だと指摘できる特徴が見いだせないのである。実際のところ史料も「ギリシアの工匠」というだけで,どのような人物が,どのようにかかわったのかは述べていない。 マインヴェルクはもう一つパーダーボーンに,興味深い教会建築を残している。ブスドルフ教会と呼ばれる建物は,今は長方形の小さな建築だが,かつては八角形の中心部から四方に十字形の腕が伸びる形をしていた。なかなかに独創的な集中式の教会といえるだろう。 しかしかつて,かの碩学クラウトハイマーも頭を悩ませた問題がある。先の『マインヴェルク伝』によると,司教はヴィノという修道院長を聖地に派遣し,イェルサレムの聖墳墓教会の寸法を調査させ,それを元にこのブスドルフ教会を建てたというのである。いうまでもなく聖墳墓教会の中核をなす建物は円堂である。この点においても,納得のいく説明を見つけるのは容易ではない。 バルトロメウス・カペレとブスドルフ教会,いずれも謎の多い作品ではある。しかしそこに,アルプスの北,神聖ローマ帝国の人々が当時つのらせた地中海への思いのほどを見て取ることができるのではないだろうか。 |
|
レオン・カスティーリャ王アルフォンソ6世の没後900年祭 久米 順子 |
|
今年2009年は,中世イベリア半島に栄えたレオン・カスティーリャ王国のアルフォンソ6世(レオン王在位1065〜,カスティーリャ王在位1072〜1109年)が没して900年にあたる。スペインでは近年この王の時代に関する出版や研究集会の開催が相次いでいる。歴史上,数多の王がいるなかで,歴史学,美術史,文学,典礼学,古文書学,古書体学など多種多様な分野の──それもスペインのみならず欧米各国の──研究者が,彼の治世に注目をよせるのはなぜだろうか。 端的に言ってしまえば,彼の治世がさまざまな意味でスペイン盛期中世のひとつの分岐点だからだろう。アルフォンソ6世は,父フェルナンド1世が推進したレコンキスタ(対イスラーム国土回復戦争)をさらに進展させた。アルフォンソは,戦闘でイスラーム軍を破ると,領土を直接支配下にいれるかわりに高額の貢納金を要求し,それをフランスのクリュニー修道会に貢いだ。16世紀にローマのサン・ピエトロが建造されるまで西欧最大の教会だった,いわゆる「第三クリュニー」の巨額にのぼる建設資金のうち,およそ半分をアルフォンソ6世が出資したといわれるほどである。それ以外にも自国内の修道院を寄贈したり,同会の出身者を教会の要職につけたり,何かとこの修道会との関係を強化した。また,いわゆる「グレゴリウス改革」に燃えるローマ教皇庁から派遣された特使の説得を受入れ,それまで用いられていたイスパニア式典礼を廃棄してローマ式典礼を採用した。それに伴い,王国内で使用される文字も,西ゴート書体からカロリング書体へと変更された。アルフォンソ6世は,イベリア半島の外(フランスとイタリア)から王妃を迎えた最初の北スペインの国王でもあった。サンティアゴ・デ・コンポステラへの巡礼路の整備が行われたのも,初期ロマネスク様式が北スペインに広く伝播したのも,彼の治世の間のことである。 1085年には,レオン王国の精神的祖先である旧西ゴート王国の首都トレドをイスラームの手から奪取し,イベリア半島史上初めて「二つの宗教の皇帝」を名乗った(ちなみにユダヤ人を含めた「三つの宗教の皇帝」の称号の使用は,彼の孫にあたるアルフォンソ7世を待たねばならない)。これは,一方では,711年にイベリア半島に侵入して以来,常に優勢を保ってきたイスラームとの勢力の均衡が,ここに来てひっくり返ったことを示している。他方では,9・10世紀の間,ヨーロッパの他地域との接触をほぼ失って孤立していた小国が,神聖ロ |
ーマ帝国が独占していた「皇帝」の称号を引っさげて西欧の最前線に飛び出したという見方ができる。 このように,アルフォンソ6世の時代には,政治史的にも文化史的にも見過ごせない大変化が目白押しなのである。近親相姦の仲とまで噂されるほど過保護だった姉,生涯で娶った5人もの妻や複数の愛人たちなど,常に女性に囲まれながら,王座を巡る兄弟間の凄惨な争いを制したその人生にも興味が尽きない。政治にも軍事にも優れた名君だったのか,はたまた『エル・シッドの歌』で描かれるような嫉妬深い小心者だったのか。個人的にはもともとアルフォンソ6世よりもその両親フェルナンド1世とサンチャ王妃の方に関心を抱いていたのだが,なにしろここ数年,関連研究が次から次へと出るものだから,すっかりこの一家の虜になってしまった。 この秋にもまだ,彼が好んで滞在した修道院の遺構があるレオン地方の小村サアグンにて,アルフォンソ6世に関する総合的な研究集会が10月に,またマドリードのコンプルテンセ大学で同王とその時代の美術をめぐるシンポジウムが11月に開催される予定と聞く。どちらの招待講演者も,悪く言えばいつもの顔ぶれに見覚えのあるような題目ばかりで新鮮味に欠ける印象だが,よく言えば大物揃いで,900年祭を締めくくるにはふさわしいといえるだろう。サアグンは,スペインにしては珍しく(なんていうと怒られるかもしれないが),早くも数年前に900年祭準備委員会を立ち上げ,来年度に予定されているクリュニー会創立1100年祭(Cluny2010)やレオン大学,ニューヨーク大学などと連携しながら,すでに数回のシンポジウム開催などを行ってきている。コンプルテンセ大学の方は,スペイン初期ロマネスクをめぐって相容れない意見を主張する中堅・重鎮が顔を合わせるため,活発な議論の応酬が期待できそうである。さらに,短時間ながら若手研究者にも発表のチャンスが与えられるとのことで,何か新しい視点が見えてくるかもしれない。今から発表論文集の刊行が待ち遠しい。 サアグンの900年祭実行委員会による ページ:http://www.alfonsovi.es/ コンプルテンセ大学のシンポジウム告 知ページ:http://www.ucm.es/centros/webs/ d437/index.php?tp=III%20Jornadas %20Complutenses%20de%20Arte %20Medieval&a=invest&d=17532.php |
|
自著を語る60 『ギリシア悲劇ノート』 白水社 2009年10月 262+ii頁 2,520円 丹下 和彦 |
|
自著を語るのは難しい。ほんとうは語らない方がよいのだろう。人が本を書く目的の一つは他人に自分の考えをわかってもらうことにあるのだろうが,書いた本人にとっては一度書いたものをもう一度説明せよと言われると,肝心なところで寡黙になり,どうでもいいところで饒舌になる。いずれにせよ読んでもらえば済むことを改めて説明するのは,やはり難しい。 本書は,ギリシア悲劇という現代日本人にはいささか馴染みが薄いかもしれないが,西欧文明を理解する上ではやはり欠かせない鍵の一つと思われるものを,改めて,しかもできるだけわかりやすい方法で紹介しようとしたものである。 ギリシア悲劇の残存作品は全部で33篇ある。これを相手にわたしたちは日夜格闘し,あれこれ議論している。作品が生まれてから今日に至るまでの2400有余年という長い時間のあいだに,作品をめぐる論議も多岐にわたり,また幾重に積み重なり,あるいは錯綜し,それが昂じて議論のための議論といった様相も呈してきた。 いうまでもなくわたしたちが取り扱っているのは悲劇のシナリオ(それを校訂したテクスト)である。それは元来板の上に乗せて上演し,視覚聴覚によって鑑賞さるべきものである。しかしそのことをついなおざりにしてシナリオ(テクスト)の字句にばかり拘泥するところが,これまでは多すぎなかったろうか。古代のディオニュソス劇場での上演をそっくりそのまま再現することは不可能だが,テクストを読んで受容する場合でもそれがドラマのシナリオであることを常に意識して,往時の上演の様子を自らのうちに再現してみるだけの想像力を持ちたい。ディオニュソス劇場の観覧席の一つに身を置いたつもりになるのも必要なことだと思われる。 さて本書で取り上げた10個の話題は,テクストを読んでいるだけでは収まらない問題,それでいてテクストの解読に多かれ少なかれ影響を与える問題を含む,そういったものである。プロロゴス(序詞)やデウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)といった劇の構成に関わるもの,俳優,合唱隊(コロス)など上演に関わるもの,シナリオの改竄をめぐる問題,素材と創作行為をめぐる問題等々,いわばギリシア悲劇を改めて演劇的パフォーマンスとして捉え直そうとするものである。 たとえば畏友川島重成氏がかねてより主張しているイ |
オカステによる息子オイディプス認知の時期の問題(ソポクレス『オイディプス王』)も,書斎ではなく劇場の観覧席に身を置いて考えたらどうなるか,という視点で再度論じてみた(第8章)。この問題については川島氏と過去に何度か遣り取りがあったけれども,すくなくともわたしのほうは最近テクスト主体の論争に手詰まりを感じるところがあった。それが今,すこしばかり展望が開けた感じがしている。 漱石や鴎外の作品の一部を借用したのは,わたし自身過去長年にわたって感得してきた女性の神秘性,不可思議性(!)が,洋の東西を問わずやはり存在するものとの感を深くしたからである。お佐代さんも美禰子さんも,ギリシア悲劇の中の女性たちに負けず劣らず存立することができる。鴎外が描き出したお佐代さんはアルケスティスのあの沈黙と共通するものがあると,これはかねてから感じていた。第6章はそれを言いたくて(それだけではないが)書いた章である。 第9章の冒頭の『三四郎』の一節は,編集子の一言に触発されたものである。当初は合唱隊の登場の仕方にしか思いはなかったのが,劇場の構造へ,デルプフェルトへ,漱石の一節へ,そしてケーベル博士にまで話が及んで,それが拙文の導入部となった。漱石はあの知識をどこから仕入れたのか。たぶんケーベル博士からだと思うのだが,わからない。ケーベル博士の周辺には,田中秀央や深田康算など古典ギリシアに詳しい人もいたのだが……。漱石自身の勉強の成果ということもあり得る。いずれにしてもそれを突き止められないままに書いてしまった(ご存じの方があればご教示賜りたい)。 こうしたことはギリシア悲劇を身近に感じてもらうためにしたことだが,あるいは浅知恵との謗りを受けるかもしれない。しかし人間の営為は,どれほど時空間を隔てようとも,ごく似通ったものであるという認識があれらの文章を引かせた。諒とされたい。 先般上梓した『ギリシア悲劇』(中公新書,2008年)では作品と真正面から向き合い,シナリオ(テクスト)を文学的に読み込むことに努めた。本書では,上に述べたように,すこしアングルを変えていわば仕事の周辺を遊覧することを試みた。「ノート」と題した所以である。 |
|
地中海世界と植物4 バルサム樹/堀井 優 |
|
バルサム樹(メッカ・バルサム)はアラビア半島南部を原産地とし,その樹脂は香料,鎮痛剤,解毒剤として効用があり,地中海世界でも広く知られ,一部の土地では栽培されていた。例えばプリニウス(23−79)の『博物誌』には,ユダヤ人の地およびローマにおけるバルサム樹についての記述がある。 表紙の図版の出典は,プロスペロ・アルピーニ(1553〜1617)の『エジプト植物誌』である。著者はヴェネツィア共和国領ヴィチェンツァの近くの町マロスティカ生まれの医者・植物学者であり,パドヴァ大学で医学を修めた後,ヴェネツィア人領事ジョルジョ・エーモに随従する医師としてオスマン帝国支配下のエジプトに渡り,1581〜84年のカイロ滞在中にエジプト各地の植物を調査して,その成果を植物誌や自然史などの著作にまとめた。『エジプト植物誌』はこの土地に見られる約50種類の植物について解説し,バルサム樹についても,樹木および樹脂の特徴とともに,そのエジプトとの関わりについて報告している。 エジプトでバルサム樹に関連して有名な場所はカイロ近郊のマタリーヤであり,伝説では聖家族がエジプトに避難してここに滞在した時に,イエスがこの樹を生やしたとされる。アルピーニによれば,バルサム樹はエジプトでは自生せず,移植しても枯れやすく,マタリーヤの |
庭園では念入りに手入れされていたという。しかしそれでも1575年にエジプト総督メシフ・パシャは,この庭園のバルサム樹が枯れていることに気づき,アラビア半島西部の聖都メッカから,新たに40本を取り寄せて移植した。ただしこれらも数年後には,庭園管理人の不注意でほとんど枯れてしまったという。 このようにエジプトのバルサム樹は,この土地とアラビア半島とのつながりを示すが,メッカのバルサム樹脂もまた広域的な交流と関わっていた。メッカはイスラーム世界の巡礼交通網の中心に位置し,10世紀以降は預言者ムハンマドの子孫であるシャリーフの政権がここを中心に半島西岸部のヒジャーズ地方を支配し,16世紀以降はオスマン帝国がこのシャリーフ政権を保護下においていた。アルピーニによれば,オスマン朝スルタンは毎年シャリーフに「金の長衣」,その息子と兄弟には金貨を贈り,シャリーフはその返礼として最高級の亜麻布とバルサム樹脂をスルタンに贈る。またシャリーフは,エジプト総督,カイロから来る巡礼団長,ダマスクスおよび「幸福のアラビア」から来る巡礼団長にもバルサム樹脂を贈るという。地中海から周辺に広がるオスマン世界,あるいはメッカと地中海をつなぐ巡礼網の一断面を示す,興味深い記述といえるだろう。 |