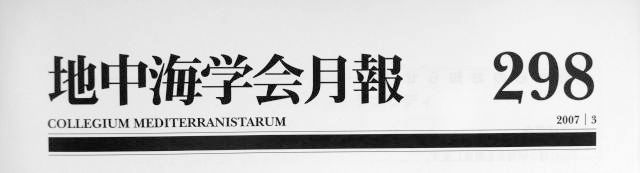

|
学会からのお知らせ
|
|
*4月研究会 下記の通り研究会を開催します。 テーマ:第三共和政期フランスのアルジェリア地方行政 発表者:工藤 晶人氏 日 時:4月14日(土)午後2時より 会 場:東京大学本郷校舎法文2号館1大教室 (最寄り駅:地下鉄「本郷三丁目」「東大前」 東大キャンパスサイト http://www.u-tokyo.ac.jp /campusmap /cam01_01_02_j.html) 参加費:会員は無料,一般は500円 地中海を南北にまたいだ宗主国フランスとアルジェリアの関係は政治・社会のさまざまな面で独特の緊密さをもつものであり,そこには直接統治と同化政策を基軸とするフランスの植民地戦略が典型的にあらわれたと見なされてきた。本報告ではこの論点を再検討するために,近年の比較史研究の成果をふまえつつ第三共和政期の植民地における地方行政のあり方を分析する。 *第31回大会 第31回地中海学会大会を6月23・24日(土・日)の二日間,大塚国際美術館(徳島県鳴門市鳴門町鳴門公園内)において下記の通り開催します。 6月23日(土) 13:00〜13:10 開会宣言・挨拶 大塚明彦氏 13:10〜14:10 記念講演 「大塚国際美術館 空想と現実の美術館」 青柳正規氏 14:25〜16:25 地中海トーキング 「巡礼と観光──瀬戸内海と地中海」 パネリスト:大原謙一郎氏/関哲行氏/田窪恭治氏/司会兼任:桜井万里子氏 16:40〜17:50 美術館見学(自由見学) 18:00〜20:00 懇親会 6月24日(日) 10:00〜11:30 研究発表 |
「テオクリトス第5歌における山羊飼い──牧人の社会的身分と人物像について」 小見山直子氏 「ヴェネツィアの貴族とスクォーラ ──スクォーラ・グランデ・ディ・サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタとヴェンドラミン家の事例から」 和栗珠里氏 「地中海地域における「声の文化」とその復興 ──コルシカ島の「ボーヂ」と「ポリフォニー」について」 長谷川秀樹氏 11:30〜12:00 総 会 12:00〜12:30 授賞式 「地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞」 13:30〜16:30 シンポジウム 「二つのシスティーナ礼拝堂」 基調報告「システィーナ礼拝堂壁画の歴史的意味」 若桑みどり氏 パネリスト:秋山学氏/園田みどり氏/真野響子氏/司会:石川清氏 *会費納入のお願い 新年度会費の納入をお願いいたします。口座自動引落の手続きをされている方は,4月23日(月)に引き落とさせていただきます。ご不明のある方,領収証を必要とされる方は,事務局までご連絡下さい。 退会希望の方は,書面にて事務局へお申し出下さい。4月20日(金)までに連絡がない場合は新年度へ継続となります(但し,会費自動引落のデータ変更の締め切りは,4月6日)。会費の未納がある場合は退会手続きができませんので,ご注意下さい。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *日本学術振興会の募集 日本学術振興会では,平成20年度採用分特別研究員および特別研究員-RPDの募集を行っています。詳細はhttp://www-shinsei.jsps.go.jp/。 |
アルファベットラプソディ 師尾 晶子 |
|
アルファ,ベータ,ガンマ,デルタ,神の字エイ, ゼータ,エータ,テータ,イオータ,カッパ,ラブダ,ミュー, ニュー,クセイ,オウ,ペイ,ロー,シグマ,タウ,ユー, それからフェイ,ケイ,プセイにオー。 アテナイオスの『食卓の賢人たち』第10巻にはさまざまなことば遊びの歌が紹介されているが,これは喜劇作家カリアスの『アルファベット劇』の一節として引用されたものである(453c-d)。歌はさらにつづく。 ベータ(Β),アルファ(Α),バー(ΒΑ)。ベータ(Β),エイ(Ε),ベ(ΒΕ)。ベータ(Β),エータ(Η),ベー(ΒΗ)。ベータ(Β),イオータ(Ι),ビー(ΒΙ)。ベータ(Β),オウ(Ο),ボ(ΒΟ)。ベータ(Β),ユー(Υ),ビュー(ΒΥ)。ベータ(Β),オー(Ω),ボー(ΒΩ)。 かつて,この作品は紀元前430年代のものと考えられていた。エウリピデスの『メデイア』とソフォクレスの『オイディプス王』に影響を与えたと,アテナイオスが記しているからである。しかし近年,『アルファベット劇』は,アテナイにおける正書法の改正をほのめかしたもので,前5世紀末から前4世紀初頭につくられたという説が提案されている(E. Pöhlmann, RhM 114(1971) 230-240; R. Rosen, CP 94(1999) 147-167. cf. C. J. Ruijgh, Mnemosyne 54(2001) 261-339)。テオポンポス(断片155)によると,前403年,アテナイの公文書の正書法は長母音と短母音を区別しないアッティカ式からΗやΩを用いるイオニア式に取って代わられた。この決議は,事実上優勢になっていたイオニア式正書法の使用にお墨付きを与えたにすぎないものであった。とはいえ教育の現場においては,これ以降,どんなに保守的な教師であっても,Ξ,ΨとΩの3文字を加えた24文字のアルファベットを教え,エ(Ε)とエー(Η),オ(Ο)とオー(Ω)の綴り方の違いを教えなくてはならなくなっただろう。そんなどたばたと混乱を風刺したのがこの劇だった,というわけである。 ところで正書法の好みの変化は,いつごろから起こっていたのだろうか。義務教育も定番の教科書も存在しなかった古代アテナイにおいては,教師の手ほどきを受けたとしても,結局のところ人びとは個々の流儀にしたがって文字を書いていたにすぎなかった。公文書の場合,文案を示した書記の好みが反映されたのか,それを書き写した工房の好みが反映されたのか,細かい事情は判然 |
としないけれど,前430年頃からアッティカ式で記された文章に若干のイオニア式の正書法や文法が混入した碑文が目立ちはじめる。そして前415年をすぎる頃には,ΤΟΥΤΟ, ΤΟΥΤΟΝと書くべきところをΤΟΤΟ, ΤΟΤΟΝと書くめずらしい綴り方も出現する。イオニア式が隆盛する中で,古風なアッティカ式にこだわる書き手が極力二重母音を避けようとした結果,このような綴り方が編み出されたのかもしれない。実際,人名や名詞では二重母音のΟΥがΟで代用されることはよくあった。さらにΤΟΤΩΝというイオニア式ともアッティカ式ともいえない綴りも出現する。流行の変遷のさなかにあって,なじんだ綴りと新しい綴りとの間で混乱が起きたとしても不思議ではない。こうした混乱は,前390年代まで散見される。 私的な碑文に目を移すと,変化の嵐は公文書よりもはるかに早く始まっていたことがわかる。いつの世も,最後まで古いものにこだわるのは役所とか政府とかといったところなのかもしれない。陶片追放に用いられた陶片を俯瞰すると,前450〜40年にはイオニア式のアルファベットの採用がちらほら目に付くようになる。そして,前410年代のものでは,サンプル数が少ないもののすべての陶片がイオニア式で書かれ,アッティカ式アルファベットを使用したものは1枚もない。この傾向は墓碑や陶器に描かれた文字の場合も変わらない。民間レベルでは前420年代半ばには,アテナイ人はアッティカ式よりもイオニア式を好んで使うようになっていたらしい。 このことは,エウリピデスの『テーセウス』(上演前422年以前)におけるテーセウスの綴り方をめぐるくだりからも裏付けられる(断片382)。劇中でアルファベットの名前を知らない人物がテーセウス(ΘΗΣΕΥΣ)を構成する文字の特徴を次のように説明する。「コンパスではかったような円があって,その真ん中にくっきりとした印があります(Θ)。二つ目はまず2本の線があって,これらをもう1本が真ん中で分けています(Η)。三つ目はくるっと巻いた巻き毛のようです(Σ)……」前420年代後半にはすでにアッティカ式のΘΕΣΕΥΣではなくイオニア式の綴り方が一般的だったのだ。 前5世紀末の公的碑文における綴り方の混乱は,日常生活での綴り方と公文書での綴り方の齟齬に書き手が困惑している様子を反映したもののように思えてくる。カリアスのくだんの歌は,前403年の決議でこの苦悩から解放された市民の安堵の気持ちを体現しているのかもしれない。 |
特別寄稿:イタリア便り サンクト・ペテルブルクの「ヴォルテール文庫」(1) アルマンド・トルノ/武谷 なおみ訳 |
|
サンクト・ペテルブルクのオストロフスキー広場は,まるで建築の教本から取ってきたようだ。中央にエカテリーナ2世の像がそびえ立ち,その背後にアレクサンドリンスキー劇場が建つ。新古典様式の見事な作品である。ナポリ出身のカルロ・ロッシの手になるもので,人生の後半を皇帝たちの都で送った建築家は,1849年にこの地で没した。劇場の後ろをはしる通りには彼の名前がついている。測量計算が完璧なことで知られる道路は,長さ220メートル,幅22メートル,通りに面した建物の高さはすべて22メートル。あまりの完璧さに思わず目をそらし,広場の右側の建物に安らぎを求める。おなじロッシの設計によるこの建物がロシア国立図書館で,3,000万冊の蔵書をほこる世界有数の図書館である。ロシア19世紀を代表する作家のほとんどすべてがここで学んだ。ゴーゴリやドストエフスキーの名を思い浮かべるだけでよい。レーニンもまた,多くの日々をここで過ごした。 だがロシア国立図書館には,ほとんど誰も知らない歴史が秘められている。皇帝たちが所有していた多くの書物がここに来たのだ。ディドロの本も収集されている(それらはエカテリーナ2世の時代に購入された)。そしてほら,半地下の防壁をほどこした閲覧室に,ヴォルテールの蔵書の「すべて」が大切に保管されている。どの本にも,彼の筆の跡がうかがえる。メモ,訂正,数々の皮肉。皮肉は痛烈で,ページを追うほど,ますます高雅な中傷へと形を変えてゆく(ルソーについては,とりわけ熱がこもっている)。ためしに1冊開いてみるだけで,かつての本の持ち主と交流しているように思えてくる。ヴォルテールの魂がまだこの辺りで,辛らつな微笑を浮かべ,書きこみをした紙の間をさすらっているような気がする。いったいどんないきさつで,これらの本はこの壁の間におさまったのだろう? ヴォルテールの蔵書はエカテリーナ2世の購入によるものだが,防壁をほどこした部屋にきちんと整理されたのは,実は最近のことである。1997年9月26日にシラク大統領が「ヴォルテール文庫」の訪問を希望したとき,彼はまだ,6,814冊の蔵書が積み上げられたふたつの大きなケースの前で,恭しく頭を下げることができただけだった。しかしその日から多くのことが変化した。では,「文庫」の歴史をざっと語るとしよう。ただし,われわれは特別閲覧室をいったん離れて,パリに向かわねばな |
らない。いや,もっと正確にいうなら,1778年2月10日のパリである。 いつもと変わらないふつうの日だった。だがその日,フランソワ=マリー・アルエがフランスの首都にやって来た。ヴォルテールというペンネームで1718年以後,世に知られるようになった思想家で,当時はもう「長老」と呼ばれていた。しかし28年このかた彼はパリには足を踏み入れておらず,ここ20年ほどは,ジュネーヴに近いフランス領フェルネーの城に居をかまえていた。 このときすでに83歳。彼の手紙は健康についての苦情であふれているが,パリ市民は狂喜した。到着の翌日,300人の訪問を受け,歓迎につぐ歓迎の嵐。彼は忠実な秘書のジャン=ルイ・ワニエールに命じて,仕事に使う本を数冊送らせている。傍には姪のマリー=ルイーズ・ドゥニ夫人がつき添っていた。姪というだけではなかったようだ(セオドア・ベスタマンが1969年にロンドンで出版した名著『ヴォルテール』の第21章によれば,彼女は愛人でもあった)。だが多くの成功の後に,ヴォルテールの生涯が尽きるときがきた。同じ年,1778年5月30日に思想家は死ぬ。いや,死んだと明言するのは誤りだろう。次の日の夜,5月31日のおそらく23時と24時の間に,6頭立ての馬車が1台,現在のヴォルテール河岸通り27番地とボーヌ通りの一角にある屋敷を出て,全速力で走り去った。そう,その馬車に「長老」がのっていたのだ。世に知られる愛用のガウンを着て,頭には,それにおとらず有名なナイト・キャップをかぶっていた。下男がひとり,横に座っていた。もしその闇夜の暗がりで,誰かが老人の顔にランタンをかざしたら,身の毛もよだつ発見をしただろう。男は死人であるばかりか,手早く防腐処理をほどこされていたのだ。死体は悪臭を放ちはじめていた。教会当局が,公認の墓地に「長老」を埋葬させないよう見張っている。だからヴォルテールはまだ,公式には生存していたのである。彼の遺体は6頭立ての馬車にのせられ,墓を求めてひた走った。フェルネーにもどるのは都合がわるい。埋葬禁止の知らせがまもなく死者のもとに届くだろう。禁止令がそこで彼を襲うのは目に見えていた。だがわれわれは馬車をこのまま走らせることにして,別のことに目を転じよう。話のつづきは,またの機会にゆずるとして。 ドゥニ夫人については先にふれた。彼女は愛人でもあった伯父の最後の数ヶ月間,彼が記す書類のすべてを監 |
|
視しつつ,残酷なほどのやり方で傍に仕えた。包括相続人に指名されていたから,「長老」が考えを変えるのをなんとしても阻もうとした。今はその資産をぜんぶ巻き上げて安全な形に変え,残りの人生に備えねばならない。伯父の財産目録のうち,蔵書はいちばん価値のある物件ではなかったが,ロシア全土に君臨する女帝が特別の関心を示した。ドゥニ夫人に鷲の鋭さがあったわけではない。むしろ鶏の脳味噌しかなかったが,商売に必要なのはただ待つことだと彼女は心得ていた。事実,ボヘミヤ貴族のフォン・グリム男爵が,エカテリーナ2世の名代として現れた。女帝が,ヴォルテールの本と書類の購入を希望しているという。エカテリーナはあらゆるものを求めてきた。思想家と交わした手紙,ピョートル大帝の伝記を書かせるために送った資料,極秘通信に用いた暗号。「長老」は,なん度か女帝に重要な政治的提言をしたことがある。たとえば1769年5月の対トルコ戦で,どんな戦車を使用すべきかの忠告まで与えている。ドゥニ夫人は,値段をつりあげることができると直感した。 しかし,途方もない購入のニュースは広がり,ヨーロッパの知識層は噂に余念がなかった。ヴォルテールの他の親戚縁者は,びた一文入らないことに我慢がならず,こうした場合よくあるように,フランス国民の自尊心に訴えようとした。ドゥニ夫人の弟である神父はコルベロンという男と組んで策を練ったが,賢明なエカテリーナに対しては,ほとんどなすすべがない。女帝は外交手段をこうじて,獲得物を手放さなかった。思想家ヴォルテールに墓を拒絶するような国は,その魂を守る資格はないと関係者に告げた。むろん蔵書のことである。一方,姪の側は,本当の意味での売却は避けるのが得策であろうと判断した。そこで,エカテリーナの使いのグリムに対し,書物は陛下に「寄贈」いたします,でも,陛下に対して抱いている敬意ゆえに,陛下の肖像が入った宝石箱をひとつ,それからロシアの想い出のために,ダイヤモンドや毛皮のような,ちょっとした品をいただけたら嬉しい,と意思表示した。 エカテリーナ2世は,ヴォルテールの蔵書を寄贈されるふりを装ったが,心の底では所有を熱望していたのだ。「想い出」の品に払う金を計上し,それで,この一件にけりをつけるようグリムに命じた。こうしたすべてが明るみに出たのは,ドゥニ夫人が1778年12月15日付けで,ボヘミヤの男爵宛の受領書にサインしているからで,彼女はダイヤモンドその他を受け取ったあと,慎みぶかくこう書いている。「……私は勇気をふるって,あれ(蔵書:編集者注)を寄贈いたしました」 いちばん大きな仕事は終わった。だが今度はパリに残されている書物ともうひとつ,ヴォルテールが学友のアンリ・リュウに終身譲渡した100冊強のイギリス関連の書を取りもどさねばならない。「長老」はこの友人を「愛する海賊」と呼んでいた。彼のために書籍その他を用立ててやったのだから,愛情の証だったのはほぼ間違 |
いない。エカテリーナは時を移さず行動にでた。たちまち部下を放って追跡調査し,フェルネーの家になかったものを見つけだした。 女帝はグリムを総監督に任命し,また,かつてヴォルテールと手書きの書籍目録作りをしたことのある秘書ワニエールが梱包に立会い,運送を指揮するように命じた。12個の巨大な木箱が必要だった。輸送ルートはエカテリーナ自身によって決められた。フランクフルトを経由してルベッカに到る(ここには1779年5月16日に到着して,エレンシュレーガー未亡人が経営する商社に運ばれた)。ドイツの港には,ニコライ・シュビン中尉が司令官をつとめる船が用意されていたはずだ。フィンランド湾の一地点,クロンスタットという小さな島に立ち寄った後,蔵書はペテルブルクに到着した。ワニエールはこの間に,肝炎を患っていた。書物を再度きちんと整理するには,数ヶ月はかかる。その年の10月末から年末にかけて,秘書は梱包を解いた。本はエルミタージュの,エカテリーナ個人の書斎の隣におさめられた。彼女はそれらがフェルネーの本棚にあったのとそっくりそのまま,同じ場所に置かれることを望んだという。 ヴォルテールの蔵書はそこで,初めのうちは尊ばれ,後に疎んじられるようになった。反動的なニコライ1世の時代(1825年〜55年)には,皇帝はヴォルテールを嫌い,彼を「老いぼれ猿」と呼んでいたほどだから,本を売り飛ばす恐れさえあった。その後,アレクサンドル2世治世下の1861年に,サルティコフ・シェドリン図書館への移送が決まり,楕円形の部屋に設置された(この図書館がソビエト時代をへて,現在のロシア国立図書館になる)。1948年までそこに置かれたが,その空間は他の珍品に場をゆずった。けっきょく本はふたつの大きなケースに収められたまま,先に述べたように,フランスのシラク大統領が恭しく頭を下げる日を待つのだ。何年か後に別の表敬訪問もなされた。フランスとロシアを代表するラファリンとカシアノフ両首相である。だがそれは2003年6月20日のことで,蔵書はすでに古い巨大なケースから出され,防壁をほどこした部屋で整理がなされている最中だった。現在はそこが「ヴォルテール文庫」と名づけられて,設立後まもない「啓蒙の世紀研究所」の核をなしている。エルミタージュ時代の書棚は作り直され,本はフェルネーの書斎と寸分たがわず,またエカテリーナもそう望んだとおりに並べられて,現在は,閲覧を希望し,貴重なメモの解読をめざす研究者の利用に供されている。ネット上にあらわれる最初の表題は,おそらくエルヴェシウスの『精神論』と『クリストフ・ドゥ・ボーモン宛,ルソーの書簡』である。 さて,特別閲覧室にはなにがあるのだろう? まず第一にそれは,われわれのもとに届けられたひとりの啓蒙主義者の,ただひとつの完全な「文庫」である。さらにそれは歴史であり,思想であり,数え切れぬほど沢山のもの。ひと言でいえば,ヴォルテールの魂なのだ。 |
ローマ帝国とビザンツ帝国 倉橋 良伸 |
|
1990年代以降,「後期ローマ帝国」に関する研究書や概説書の出版が相次いでいる。これは,P.ブラウンを牽引役とする「後期古代(Late Antiquity)」に対する関心の高まりを反映するものであろう。 さて,今回,特にここで取り上げたいと考えるのは,ローマ史における「時代区分」である。封建制度の成立をめぐる論争を代表とする,「古代」と「中世」に関する時代区分ではなく,あくまでローマ史についての論点整理のための一提案を意図するものである。 瑣末なことと思われがちだが,これから見るように,特にローマ史を専門とされない方々にとっては,意外に重要な問題なのである。しかも,実は専門家にとっても避けて通れない課題である。なお,建築史や美術史の分野においては,以下に述べる内容とはまた異なる区分がなされるが,取り上げる余裕がない。 ローマ史における時代区分といえば,大きく共和政期と帝政期に分け,さらに帝政期を「プリンキパートゥス(元首政=帝政前期)」と「ドミナートゥス(専制君主制=帝政後期)」に分けるというのが一般的なものであろう。そして,1453年まで存続した「中世ローマ帝国」を「ビザンツ帝国」と呼んで区別する。これらは,ローマ史研究があまりにも長期間を対象とするがゆえに,便宜的に呼び分ける必要から発生している。 一方で,ドミナートゥス時代を「後期ローマ帝国」や「初期ビザンツ帝国」と呼ぶ研究者や概説書も少なからず存在する。あるいは,395年の東西分割後については,「西ローマ帝国・東ローマ帝国」と呼ぶことも珍しくなく,この「東ローマ」を「ビザンツ」と同一視することも多い。しかも,ビザンツとは近代以降の呼び方であり,当時には存在しなかった。さらに,ビザンツ帝国は1204年に起きた第4回十字軍による帝都コンスタンティノポリス占領をもって滅亡した,とする研究者もいる。 既にこれだけで,特に専門外の人間にしてみれば,混乱するのも無理はない。しかも,近年の「帝国論」の高まりもあり,確定していると思われがちな共和政期についても,末期には「帝国化」していたとされる。 専門家の立場から見ても,年代が明記されていないと,研究書のタイトルだけでは,扱われている時代が判断できないことがしばしばある。 帝政期を前後に分ける根拠は,後期における変容を無 |
視しえないことにある。ただし,専門的な議論はここでは省略するが,後期における皇帝のあり方を「専制君主(ドミヌス)」と見なすのは,大いに問題ありとする研究者が増えている。そのため,「ドミナートゥス」という呼称は明らかに時代遅れとなった。したがって,前期における皇帝を「元首(プリンケプス)」と見なし,「プリンキパートゥス」を「ドミナートゥス」との対概念として捉える歴史認識にも問題が生じるわけである。 では,帝政後期において既に「ビザンツ化(=ギリシア化)」が始まっていたと考え,「初期ビザンツ」と呼ぶことに問題はないか。この呼称では,395年から476年まで存在した「西ローマ帝国」もビザンツ帝国と呼ぶことになってしまう。もちろん,476年まで西ローマとビザンツが並存したと見なすのは無意味である。言うまでもなく,西ローマと東ローマは対概念だからである。 こうした混乱を避けるためには,「帝政前期・帝政後期」という呼称が最も無難なように思われる。この帝政後期を「後期ローマ帝国」と呼ぶわけだが,帝政前期を「前期ローマ帝国」と呼ぶ研究者が見あたらないのは,「ローマ帝政史」と言えば,本来的にはこの前期を対象にするという歴史認識に影響されている。それは,後期を「初期ビザンツ」と呼ぶことにも相通じる。また,中世ヨーロッパには「神聖ローマ帝国」が存在したことも大きいと言えよう。したがって,7世紀以降をも「中世ローマ帝国」と呼ぶ歴史観も有り得るのではないか。 なお,近年では,イスラーム勢力が地中海世界で台頭する7〜8世紀を中世への移行期と見るのが学界の主流となっている。日本では紹介されることが少ないが,当該期に関する研究書も盛んに出されている。 だが,まだ問題は残っている。帝政後期に存在した二つの帝国を何と呼ぶべきか。実は,欧米の研究では,単に「西の帝国・東の帝国」と呼ぶのが一般的になっている。つまり,476年まで帝国領土として存在した西半分を東方と区別するために「西の」と加えるのであり,「西ローマ帝国・東ローマ帝国」という二つの国が存在したとは見なさない。あくまで一つの国を西と東に地理的に分けるに過ぎない。476年以降,東ローマ帝国だけ残存したと見るのではなく,ローマ帝国が東方において存続したと見るのである。「西ローマ・東ローマ」という呼称も既に時代遅れになったと言うべきだろう。 |
読書案内:山田幸正 エミール・ハビービー著/山本薫訳 『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』 作品社 2006年12月 |
|
まず「悲楽観屋」というのはいったい何だろうと誰もが思うのではないだろうか。主人公のパレスチナ人の名前が「サイード・アブー・ナハス・ムタシャーイル」で,その最後のムタシャーイルが家名にあたり,「楽観屋」と「悲観屋」という二つの言葉を混ぜ合わせた造語で「悲楽観屋」。ちなみに,名のサイードは「幸せ者」で,その次のアブー・ナハスは「悲運の父」の意。つまり,この主人公の名前は,屋号を「悲楽観屋」といい,「悲運な父」をもった「幸せ者」となる。この名前自体,なんとも矛盾と混乱に満ちている。この主人公がパレスチナに生まれ,イスラエル建国やそれに続く中東戦争など,不条理に満ちた生を体現していく。ティムールの時代まで遡るこの一族には,「悲観」と「楽観」の二つの性質が付きまとい,サイード自身も悲観と楽観の違いが分からず,いつも「俺は一体どっちなんだ」と自問している。どうみてもこれ以上不幸なことはないことについても,「こうなってよかったよ,違うふうにならなくて」と考える。また,イスラエル軍による不条理な出来事も,800年以上前の十字軍とマムルーク軍の時代に起きた事に比べれば,慈悲深いところがあるといい,この世に人間の血ほど聖なるものはなく,だからこの地が聖地と呼ばれるという。なんとも形容しようがない現実認識であろうか。しかし,過酷な現実に晒され続けると,人間このような感覚でも持ち出さないと,生き残れないのかもしれない。 この作品のなかで次々に描かれている事件や舞台,設定が,ほんとうにあった出来事を映していることや,作者本人が直接経験したことに基づくものだろうということも容易にわかった。だからといって,パレスチナの歴史や社会に疎い者にとっては,本文の字面だけではこの作品の本質はとうてい理解できなかったであろう。本書には,異例と思われるほどの脚註が補われていて,これが大いに役立つ。もともと註は付けられていたようだが,それ以外の箇所にも,訳者による丁寧な解説が添えられていることで,この小説が膨大な事実の上に構築された作品であると理解できるだけでなく,現代世界において最大の争点となっている「パレスチナ」をその歴史的・社会的な背景を含めて多少なりとも理解する手がかりとなっている。しかし,その一方で,アラブ・イスラムの古典に明るいハビービーならではの軽妙な語り口と文体 |
に合わせるような語呂合わせ的な言葉遊びや,物語の本筋から外れたような挿話が随所にちりばめられていて,それはそれなりの魅力であるとも言えるが,アラブ文学に慣れない者にとっては多少辛く感じられた。 訳者あとがきによれば,本書の著者エミール・ハビービーは,1921年,地中海東端の港町ハイファに生まれ,48年以降もイスラエル国籍をもってその地に留まったパレスチナ人,いわゆる「アラブ系イスラエル人」で,イスラエル共産党を主な舞台に,3期20年間にわたり議員を務めるなど,政治家として,またジャーナリストとして活躍した人物である。小説家としてはあまり多くの作品を世に出しているほうではないようだが,「常に時代と社会の変化を映し出す作品を発信し続け」,激しく対立しあうPLOとイスラエルの双方から賞を受けるという,まさに「生き残る」という命題を常に突きつけられているアラブ系イスラエル人の苦悩を真正面に受け止めながら,自己表現を続けていった人物であったと思われる。彼の墓碑には「ハイファに残る」と刻まれているという。 作品自体は三つの部分にわかれ,それぞれイスラエル共産党の文芸誌に掲載された後,単行本として出版されたもので,アラブ諸国で大きな反響を得たという。時はまさに70年代の前半で,ロッド空港銃乱射事件,ミュンヘン・オリンピック村襲撃事件,さらには第四次中東戦争などが起こり,ハビービーらイスラエル国内に残るパレスチナ人たちは,難民となった同胞たちのゲリラ闘争からも孤立し,自らのアイデンティティを失おうとしていた時期と重なる。イスラエルという国家の成立とその社会内部に満ちた矛盾と不条理に対して,直接的な表現でただ訴えるのではなく,ハビービーは「痛烈な諧謔精神をもってイスラエルに生きるパレスチナ人の日常を描いた」のである。「祖国にあって祖国を喪失する,敵国の市民として生きる」,そうした痛ましいまでの生をおどけたような表現でぶつけてこられると,余計にその現実の凄まじさが強烈に印象づけられるようである。現代アラブ文学・パレスチナ文学についてまったくの門外漢ではあるが,現代社会の一つの深部に触れる一冊としてお勧めしたい。 |
|
表紙説明 地中海の女と男4
トスカナ大公妃マルゲリータ・ルイーザ/北田 葉子 |
|
この女性は,マルゲリータ・ルイーザ・ドルレアン・デ・メディチ(1645〜1721),トスカナ大公コジモ3世の妻である。この夫婦には二人の息子がおり,どちらも結婚したものの子供は生まれず,メディチ家は断絶することになる。 家系の存続を望むコジモ3世がそれ以上子供を作れなかった最大の原因は,妻にある。彼の妻マルゲリータ・ルイーザは,アンリ4世とマリー・ド・メディシスの息子であるオルレアン公ガストンの娘であり,ルイ14世の従妹にあたる。トスカナ大公国とフランスの関係強化のためのこの結婚は,彼女の望むものではなかった。1661年に16歳でフィレンツェにやってきたマルゲリータ・ルイーザは,夫コジモの努力にもかかわらず,彼に冷たくあたった。長男は誕生したものの,母となった彼女は,相変わらず夫に冷淡で,怒りっぽいままであったという。コジモ3世は彼女をポッジョ・ア・カイアーノの別荘に隔離したが,この時期に彼女は長女を身ごもった。妊娠を知った彼女は,フランス人の馬丁と逃亡事件を起こし,失敗すると食事を拒否して自殺しようとした。本当に夫が嫌いだったのだろう。 1670年にコジモは大公の位を継ぎ,その2年後には次男が生まれた。しかし彼女は軟化せず,大公妃となってますます傲慢になり,政治権力を得ようとした。それに失敗すると,大公からどんなひどい仕打ちを受けたかを,フィレンツェの宮廷でも,そしてフランスの宮廷に |
も訴えはじめた。彼女は再び別荘に隔離された。その時彼女は,もう決して宮殿には戻ってこないと誓ったと言う。 実際,彼女は戻ってこなかった。二人の男子をもうけて既に家系は安泰だと思っていたコジモ3世とルイ14世は,スキャンダルとなった彼女をフランスに戻し,修道院で余生を送らせることに決めたのである。1674年,彼女はフランスにもどった。しかし話はこれで終わらなかった。モンマルトルの修道院に入った彼女は,そこで交際を広げ,夫を笑い者にし,ルイ14世もそれを信じた。彼女は宮廷に出入りするようになり,宮廷生活を楽しんだ。護衛のような身分の低い者とも関係を持ったと言う。この行跡はルイ14世に知られ,再び修道院に閉じ込められた。しかし彼女は,修道院に火をつけようとしたり,馬丁を彼女専用の侍従にするなど,妻のスキャンダルを恐れるコジモ3世を悩ませ続けた。コジモはルイ14世に,彼女を監視するよう繰り返し嘆願した。ついにルイ14世は,1692年,彼女をパリ郊外の修道院に入れることを承諾した。そこで彼女は1721年の死の時まで暮らすことになる。 その後コジモ3世が家系断絶の危機を悟ったときには,既に遅かった。彼女は遠くパリにいたし,厳格な信心家であるコジモには離婚もできなかった。こうして彼女は自らの意志を貫き,夫を遠ざけ,その結果,メディチ家断絶の一因となったのである。 |