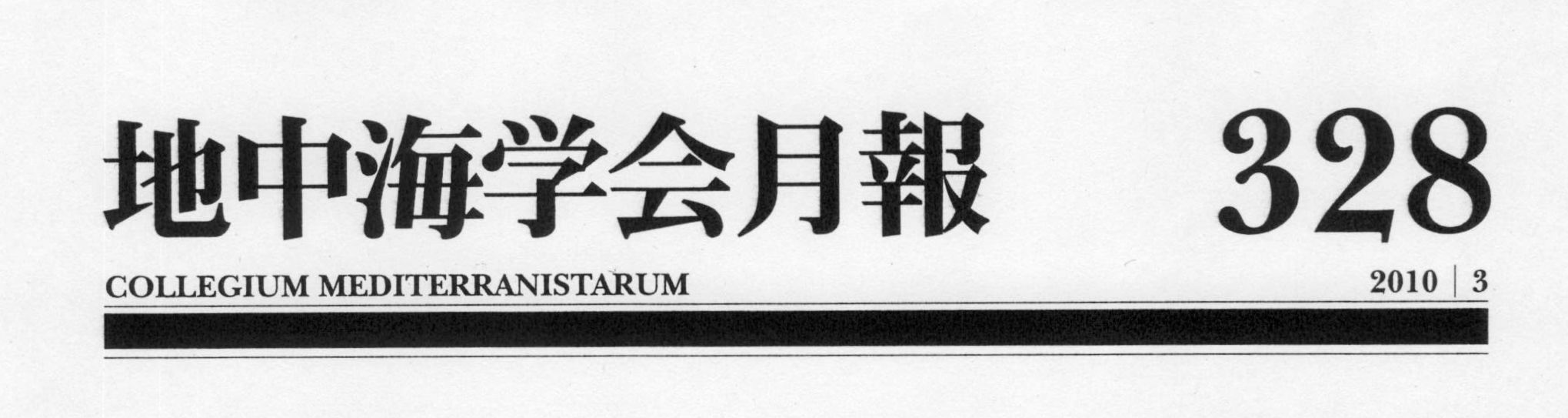|
*4月研究会 テーマ:西欧中近世における像(イメージ)の生動性をめぐって 発表者:秋山 聰氏 日 時:4月24日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 参加費:会員は無料,一般は500円 近代以降,絵や彫刻は美術館・博物館に設置され,不動であることが自明なものとされてきた。しかしかつては,絵にせよ彫像にせよ,様々に生動性を示しうるものと捉えられていたことが,諸々の文献史料からうかがわれる。中近世西欧における造像行為や像を用いての宗教的行為と,像が動いてくれるかもしれないという偶像崇拝にもつながりかねない期待との相関性について若干の考察を行なってみたい。 *春期連続講演会 ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)において春期連続講演会を開催します。各回,開場は午後1時30分,開講は2時,聴講料は400円,定員は130名(先着順,美術館にて前売券購入可)。 「地中海世界における異文化の交流と衝突」 5月1日 西洋化するイスラーム世界,イスラームを抱え込むヨーロッパ──近現代における展開 飯塚正人氏 5月8日 中世シチリアのノルマン王とイスラム教徒──異文化の共存と対立 高山博氏 5月15日 中世スペインの王都レオンの芸術活動 ──レコンキスタの戦いとロマネスク様式の形成 安發和彰氏 5月22日 イタリアにおけるゴシック建築の受容と拒絶 石川清氏 5月29日 イスラム建築にみる異文化的要素の受容と展開 山田幸正氏 *第34回大会 第34回大会を東北大学マルチメディアホール(仙台市青葉区川内41)において下記の通り開催します。なお,前号でご案内したプログラムに一部変 |
更がありますので,ご注意下さい。 6月19日(土) 13:00〜13:10 開会宣言・挨拶 13:10〜14:10 記念講演 「古代地中海世界のローマ人 ──社会史的考察」 松本宣郎氏 14:25〜16:25 地中海トーキング 「島の魅惑──ああ,松島や」 パネリスト:浅野和生/佐藤弘夫/芳賀京子/和栗珠里/司会:安發和彰各氏 19:00〜21:00 懇親会(秋保温泉蘭亭) 6月20日(日) 10:00〜11:30 研究発表 「オーセールの大判絹錦《タカの図》──布が伝えるビザンティン文化の軌跡」 山中良子氏 「ギベルティからベルニーニへ──鋳造された蜥蜴のモチーフをめぐって」 佐藤仁氏 「舟運都市ヴェネツィアの近代化──19世紀から20世紀初頭を中心に」 樋渡彩氏 11:30〜12:00 授賞式 地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞 12:00〜12:30 総会 13:30〜16:30 シンポジウム 「フロンティア──周縁か中心か」 パネリスト:櫻井康人/芳賀満/柳原敏昭/司会兼任:高山博各氏 *会費納入のお願い 新年度会費の納入をお願いいたします。自動引落の手続きをされている方は,4月23日(金)に引き落とさせていただきます。ご不明のある方,領収証を必要とされる方は,事務局までご連絡下さい。 退会希望の方は,書面にて事務局へお申し出下さい。4月12日(金)までに連絡がない場合は新年度へ継続となります(但し,会費自動引落のデータ変更の締め切りは,4月6日)。会費の未納がある場合は退会手続きができませんので,ご注意下さい。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 |
|
写真の墓標 ──杉本博司とイタリア── 松原 知生 |
|
人に専門を尋ねられればイタリア絵画史と答えるようにはしているが,このところいささか脱線気味で,地中海的明朗性とはかけ離れた日本の「湿潤」な骨董文化,とりわけ作家や芸術家たちの骨董愛好について,いつ書き上がるとも知れない本を書いている。その中でも特異なコレクターとして際立っているのが,《海景》をはじめとする静謐な写真作品で知られる杉本博司(1948〜)である。デジタルメディアが氾濫する現代美術界にあって,あえて銀塩写真というアナログ/アナクロなメディウムにこだわり,しかも自らの作品を自身の所蔵する骨董品と統合することによってクロノロジカルな時間観に揺さぶりをかける,真の意味での「時の撹乱者(アナクロニスト)」杉本。そんな彼と,筆者の(一応の)専門であるイタリアとのかかわりについて考えてみたい。 まず思い浮かぶのは被写体としてのイタリアである。たとえば《海景》シリーズではイタリアの海岸も撮影場所に選ばれているし,《建築》シリーズにはイタリア建築も含まれる。とはいえ,これらの連作では世界中の海や建築がモチーフとなっており,しかもいずれのケースでも,対象がもつ固有の空間性や時間性を濾過あるいは溶解させることが目指されている以上,イタリアという時空にこだわる必然性は乏しい。 では撮影ではなく鑑賞の対象としての,つまり写真家ではなく骨董者としての眼から見たイタリアはどうだろうか。杉本のコレクションにおいては従来,日本の宗教美術品が際立っていたが,昨年の『歴史の歴史』展においては,杉本自身が表装して軸物に仕立てた14世紀ヴェネツィアのものとされるマリア像ミニアチュールが,織部の燭台とともに展示されていた。彼はこのような取り合わせを,キリシタン大名の高山右近が茶会に掛けたであろう「マリア観音像」として構想したという。杉本は従来,アニミズムや古墳文化から神道へ,さらには仏教へと至る,古代日本の宗教的霊性の過渡期に関心を抱いてきた(それを最も端的に物象化したのが,直島の護王神社における光学ガラスによる「光の」階段である)。そこにイタリアのキリスト教絵画が加わることで,その視座が一挙に近代へと拡大されるとともに,時間の撹乱が空間の撹乱,つまり和洋の「さかいをまぎらかす」(珠光)ことと重ね合わされているわけである。 仮想の茶会における道具の取り合わせから,現実の展覧会におけるインスタレーションへと今一度目を向けてみた場合に注目されるのが,2007年にウーディネ近郊 |
のヴィッラ・マニン現代美術センターで開催された個展である。この館は,1797年にナポレオンがオーストリアとともにカンポフォルミオ条約に調印した場所であった。個展では,《肖像》シリーズの1点であるナポレオン像が,彼が寝起きした「ナポレオンの間」に展示された。生身のナポレオンから型取りされた石膏鋳型,をもとに成形されたマダム・タッソーの蝋人形,をもとに撮影された杉本の写真は,インデックス記号としての痕跡性を入れ子状に孕んだ「遺影」である。それがやはり一種のインデックス記号である「ナポレオンの間」に掛けられることで,そこに棲まうゲニウス・ロキと化したナポレオンが「影向」する依代のごとき身体性を発揮することになる。だが,蝋人形のもつ「嘘臭さ」をも倍加した杉本作品(正調モダニストを自任する杉本にはキッチュへの志向が両義的に同居している)は,こうした降霊/賦活の物語も結局は単なるフィクションにすぎないことを同時に暴露してもいるのである。 ところで,以上のような制作/蒐集/展示という三つの契機の背後にある彼独自の写真観や時間観の形成それ自体にも,イタリアでのある体験が濃い影を落としているように思われる。かつて北イタリアの海岸を旅していたある日,彼は海辺の古い墓地に出会う。墓石には楕円形の小さな遺影がはめ込まれ,ガラスで封印されていた。風雨に曝され褪色し,消え入りそうなこれらの写真を見るうちに,杉本は奇妙な錯覚に陥ったというーーもともと墓石にはガラスしかはめ込まれてはいなかったのだが,死者の霊が時間をかけて次第に銀色の像として浮かび上がってきたのだ。 アドリア海の海景写真を海辺に設置してあえて潮風に曝し,古色による(もうひとつの)景色がそこに生成するのを待つという,《Time Exposed》の特異な試みは,和骨董における古色の美学のみならず,この地中海での体験と無関係とは思えない。制作の過程で「露光」され,屋外に「曝され」,さらに美術館に「展示」されることで,三重のexpositionを経た《Time Exposed》が,『時間の終わり』展図録の巻頭に(今一度)「顕示」されているのは,決して偶然ではない。この朽ち果て苔むしたような「瀕死の」写真は,「写真の死」の立会人を自任する杉本が,「時間の終わり」の「始まり」に建てた,逆説的な写真の/写真による墓標である。そしてその背後には,彼がイタリアの墓地で出会った「死の写真」の残像が仄見えるのである。 |
|
ローマのユダヤ人 藤崎 衛 |
|
昨年(2009年),ローマのテンピオ・マッジョーレを訪ねた。20世紀初頭,テーヴェレ川のティベリーナ島に沿う旧ゲットーに建てられたローマ最大のシナゴーグのことである。すぐ近くに常駐している数名の憲兵隊員(カラビニエーリ)は,気のせいか他の地区で見かけるときよりも神経質そうにみえた。1982年にここで起きたテロからは年月を経たのだが,常に警備を必要としているのがうかがえる。 付属するローマ・ユダヤ博物館のチケットにはシナゴーグのガイド付き入場料も含まれているので,まず博物館でローマのユダヤ人の歴史と生活について知識を深めてから(別の小さめのシナゴーグも見学できる),ガイドとともに大きなシナゴーグに入るといい。男性は被り物のキッパーの着用を求められるので,時々ずれ落ちはするのだがそれを頭に載せておく。ガイドの話は会堂建築の話から始まるとしても,やがて話題は否応なくローマのユダヤ人が見舞われた悲劇へといたるだろう。第二次大戦末期,イタリアの無条件降伏が発表されると,ナチス・ドイツ軍はローマを制圧して千人を超えるユダヤ人をアウシュヴィッツへと送ったのであるから。 ところで今年1月17日,教皇ベネディクト16世がこのシナゴーグを訪れた。報道によれば,教皇の訪問に対してユダヤ人の反応は冷ややかだったという。このような反応の背景には,ひと月前,ナチスによるホロコーストを公然とは断罪しなかったとされる第二次大戦中の教皇ピウス12世を「尊者」とする手続きが開始されたことがあるようだ。ピウス12世については賛否いずれの評価もあり,ユダヤ人が求めるように当時の教皇庁の資料が全面的に公開されるまでは,あるいは公開された後でも,論争の火種となり続けるだろう。 列聖に関わる手続きといえば,前教皇ヨハネ・パウロ2世の列福調査が「ただちに聖人に!」(Santo subito!)という大衆のかけ声も後押しとなって進行中のようである。そして今回のベネディクトのシナゴーグ訪問は,このヨハネ・パウロ2世に続く,教皇としては二度目の試みであった。調べなおしてみると,1986年にヨハネ・パウロを迎えた当時の主席ラビはエーリオ・トアフという人物であった。この名前には見覚えがあった。2007年に騒がれた「トアフ事件」の当事者,イスラエルの大学教授アリエル・トアフの父親としてである。ここから話は中世に関係してくる。 |
トアフ事件とは,2007年,アリエル・トアフの著書『血の過越し』(Pasque di sangue)の出版が引き起こした論争のことである。発端は,著者が15世紀後半のトレントでおこなわれた儀式殺人事件の裁判を取り上げて,急進的なユダヤ人によるものだとしても儀式殺人があった可能性は否定しきれないと表明したことにある。このトアフの主張に対して擁護する者たちもわずかにいたものの,多くの批判的意見がイタリアやイスラエルのマスメディアをにぎわし,上述の元主席ラビである父エーリオまでも息子の書物を激しく非難するほどであった。著者はやむなく自著の流通を中止させ,翌年,穏便な論調に書きなおした第二版を出すことで事態は沈静化する。カトリック当局からは,中世のこととはいえユダヤ教とキリスト教のセンシティヴな問題だからであろう,この問題については目立った反応は見られなかった。 しかし実際,トレントの儀式殺人事件では教皇は意見を求められ,裁判に関わらざるをえなかったのである。このとき,教皇は儀式殺人に懐疑的であったが,理由の一つには,教皇のひざ元であるローマのユダヤ人たちの執りなしがあったといわれている。そうなると,中世ローマのユダヤ人と教皇との関係が気になってくる。中世のことゆえ不明な点も多いのだが,12世紀後半にトゥデラのベンヤミンというユダヤ人が著した旅行記が,ある興味深い情報を提供してくれる。ローマのユダヤ人の中には,教皇の役人として教皇庁に仕えていたラビたちがいたというのである。また,12世紀から13世紀にかけてインノケンティウスを含む多くの教皇たちが,ユダヤ人に危害を加えぬようにとの教令を発し続けたという事実もある。他方で,13世紀初頭の教皇インノケンティウス3世が第四回ラテラーノ公会議でユダヤ人章の着用を義務付けたことはよく知られている。 したがって,中世における教皇のユダヤ人に対する態度は,ときに好意的でときに抑圧的にみえるものだったといえる。だが,ユダヤ人をキリスト教徒からはっきり区別をするという点においては一貫していたのであり,このため文書や政策として具体化する際に,コインの両面のように教皇の立場が両義的にみえてくるのであろう。残された文書史料の文言を表面的にたどるだけでは,ユダヤ人と教皇の関わりを正確にとらえることはできない。今後,中世における両者のかかわりをより慎重に,より具体的に調べてみようと考えている。 |
|
西洋中世のアンソロジー考 ──ビザンツ12世紀の詞華集(フロリレギア)から── 草生 久嗣 |
|
異なる著者の既存の作品(集)から,テキストを選び集めたアンソロジー(フロリレギア)には,いわゆるモノグラフとは違った形でテキストを伝え広めていく力がある。現在の我々は,大量複製が可能な活字印刷本に慣れているため,ともすればこうした文選集について,重要な抜粋だけを並べた入門あるいは資料参考書とみたり,他人の仕事をまとめただけの二次創作などと軽視しがちである。しかし中世以前のヨーロッパでその編纂は有為の大事業であり,文化成熟の一つの形であった。よく知られるように,中世を通じて書物は稀少で極めて高価であり,その作製に用いるパピルスあるいは羊皮紙,写字生たちへの支払い,装飾や装丁にかかる費用も莫大である。しかも編集作業の前提には,豊かな文芸作品の伝統,編集者たる博識な知識人集団,十分な書誌情報や公私の蔵書,そしてアンソロジーを必要とした読者層の存在など,当時の得がたい知的資源の存在が欠かせないのである。この条件下で最大限の知的資本を投下して集められたテキスト群には,現代の同種の出版とは比べられない重みがある。その意味でビザンツ帝国が早くからアンソロジー,辞書,百科全書,叢書の出版に秀でていたことには,同帝国の経済力と文化活動の精華が現れているといってよい。 十年近く前の本月報(209号)コラムで,筆者はビザンツ帝国の異端学者エウティミオス・ジガベノスを紹介した。ジガベノスは首都コンスタンチノープルの宮廷で,皇帝アレクシオス1世(在位1081〜1118)の命令を受け,『ドグマティケー・パノプリア(教義の完全武装)』を編纂した神学者である。これは二十名を超える教父著作から,異端論駁に有用な大小数百点を越すテキスト断片を選び出し,配列しなおした百科事典的著作であった。ビザンツ帝国教会では,教義論争に際して主張の論拠を示すため,聖典・教父古典からの抜粋を集めた神学的詞華集(フロリレギア)を作成してきた伝統があり,同書もその流れにつらなる。ジガベノスは神学者集団による編集委員会を任され,おそらく1100年ごろより10年近く時間をかけて同書を編んだと思われる。 神学上の重要テキストを含むため,『パノプリア』は文選・資料集として人気を博した。たちまち類書が発行され,英国の歴史家マグダリノによれば同書収録の抜粋テキストを丸暗記した読者もいたらしい。あるビザンツ |
人神学者の著書に教父古典からの引用と断ってある部分が,実はジガベノスの『パノプリア』所収の古典テキスト断片を写したものだったこともある。聖山アトスやヴァチカン,欧州各国に写本が伝わり,またその時期も12世紀から18世紀と幅広い。トロント大学中世研究所発行の『ビザンツ期写本目録(Greek Index Project)』によれば,二百点近い関連写本が残されているという。中世にあってアンソロジーは,貴重な選ばれしテキストの束として,大変重宝されたのである。しかしながらその後,出版規模の拡大により多くの人々が本を廉価に手にとるようになり,活字出版がテキストメディアの主流になると,中世アンソロジーの編集者たち・写字生たちの苦労は偲ばれなくなってゆく。ごく最近までジガベノスや『パノプリア』に学術的関心が払われなかった原因の発端がここにある。 これまで筆者は欧米圏の行く先々で,できる限り『パノプリア』写本の現物に接するよう努めてきた。こうした写本巡りにより,研究課題であった写本間の異同の確認作業とは別に,アンソロジー的書物とそこに含まれるテキスト群の価値を,書体や校正も様々なテキストに触れて実感できたように思う。写本それぞれが,書物の量も乏しく一冊一冊が貴重とされた時代に,集められたテキスト断片を尊重し,いちいち丁寧に写そうとした写字生たちの仕事の成果と見えたからである。 写本の現物にあたることがかなわなかった場合にも,マイクロフィルム,ファクシミリ,デジタル画像など複製品の力をかり,現在までに重要なものを中心に三十近い写本の表情をみてきた。幸い,西欧諸国の専門図書館では複製品の頒布にも力を入れている。また米国のヴァチカン・フィルム・ライブラリー(セントルイス大学図書館内)のように法王庁図書館所蔵の重要写本数千巻分のマイクロフィルムのコピーを備えて,自由な閲覧を許す施設も存在する昨今,画像イメージのアクセスに際してそれぞれに多大な恩恵をこうむった。欲をいえば,画像データをインターネット上に公開する電子図書館の構想がよりいっそう進展することを期待するが,それも時間の問題であろう。中世的アンソロジーの写本文化は途絶えたが,こうして集められたテキスト群は,印刷・写真・電子画像へとメディアをわたり歩きながら,これからも西洋中世の知的精華を語り継いでいく。 |
|
コルシカ島の巨石構築物 長谷川 秀樹 |
|
コルシカ島に人類が居住していた痕跡は1.2万年前から伺える。発掘されたものとしては,島最南端のボニファシオ近辺で1966年に発見された女性の遺骨(約8200年前)があるが,この時代,どういう人々がどういう生活を営んでいたのかについての詳細は解明されていない。 しかし,先史時代(préhistore)の末期である新石器時代(néolitique コルシカ島では紀元前5700〜同2000年)と原史時代(protohistoire)最初の青銅器時代(âge du bronze紀元前2000〜同800年)には,多数の遺跡を見ることができ,その多くが巨石構築物(mégalitique)である。出現時代順に概説する。 巨石構築物は英国のストーンヘンジやフランス・ブルターニュ地方のカルナックなどヨーロッパ北西部,特にケルト文明との関連で位置づけられることが多いが,実は,地中海沿岸地域にもそれは分布する。大まかにはフランス南西部(主にガスコーニュ地方)から地中海沿岸(ラングドック地方やプロヴァンス地方),コルシカ島およびサルデーニャ島,イタリアのリグリア,トスカーナ地方,スイスのアルプス山中などにも巨石構築物の遺跡を見ることができる。サルデーニャ島のヌラーゲは地中海地域の代表的な巨石構築物であろう。 ドルメン(dolmen コルシカ語ではスタッツォーナstazzona) 板状の巨石を数枚箱状に組み合わせた構築物で,そのほとんどが墓としての埋葬用に造られたとされる。ヨーロッパではケルト圏でよく見られるが,コルシカ島では南西部サルテーヌ(Sartène, Sartè)の近くのフォンタ |
ナッチャ(Fontanaccia)にある。高さ1.8m幅1.6m奥行き2.6mの箱型。天井は一枚岩で,側面は6枚,前後面は2枚の合計9枚の板状の巨石を数え,その総重量は15tと言われる。 メンヒル(menhir コルシカ語ではスタンタールstantaru) 柱状の人物像,上部には目,鼻,口などの人間の顔のような表情が彫られ,顔部分の下から下部までには剣のようなものが彫られているのが特徴。これはフランス北西端のブルターニュ半島でよく見られる遺跡だが,コルシカ島でも主に南部を中心に十数箇所の遺跡がある。中でもサルテーヌ近郊にあるフィリドーザ(Filitosa),カウーリア(Cauria)では何体ものメンヒル像が見られ,壮観である。 トッレ(torre) 巨岩と中小のレンガ状に切り出した石を組み合わせてできた青銅器時代の構築物。一部の遺跡の形状が上から見ると半円形であり,丘陵地の頂上におおく立地していることから,サルデーニャ島のヌラーゲとの類似性も指摘されたが,ヌラーゲのように巨大なものではなく,また居住用というよりは貯蔵用に使用されたと見られている。コルシカ島南西部に良く見られ,特にポルトヴェッキオ(Porto-vecchio)近辺に多数見られる。 カステードゥ(castellu, casteddu) トッレが多数集合し,一種の集落を形成したもの。ポルトヴェッキオ近郊のアラーデュ(Arraghju)や南部山岳地帯にあるクグルーツ(Cucuruzzu)が代表的。 このようにコルシカ島は先史・原史時代の遺跡が多数,古代や中世の遺跡と共存している。歴史巡りに島を訪れるのもまた興味深い旅となるであろう。 |


 フォンタナッチャのドルメン フィリドーザのメンヒル ポルトヴェッキオ近郊のトッレ (写真は全て筆者撮影) |
|
自著を語る62 『寛容なる都 コンスタンティノープルとイスタンブール』 春秋社 2008年11月 270頁 2,500円+税 野中 恵子 |
|
私を「ビザンツ」や「イスタンブール」に向かわせた第一の伏線が「クルド問題だ」と言えば,少なからずの人がいぶかしがるだろう。理由はこの問題を,この土地の歴史とともに変遷してきた民族・宗教・権力の構成状況と,「近現代の中東問題」以外の対外関係を見ず,判断するのは無理なのだ,という確信に尽きる。言わば,建物の下の遺跡を掘り起こすかたちでトルコの民族問題の根本に迫るのが,私の「ビザンツ=オスマン=トルコ共和国」の連続性・一体性を追う取り組みである。 第二は,日本社会は外部に対する窓の開け方が偏狭すぎることへの反発である。例えば「トルコ」という大国や,「イスタンブール」という大都市の評価も矮小的で,ここは日本でありながら,これらが「西欧」に対して卑下される視点から拭われてはいない。この「トルコ」が何であり,「イスタンブール」が何であるかを,直接のやり取りの中で考察する必要がある。そうすれば,クルド問題にしろローマ帝国にしろ,巷で言われてきたこととは違う,新鮮な解釈も生れ出てきうる。 「イスタンブール」はコンスタンティヌス大帝の遷都により,イタリアの「ローマ」に対する「新ローマ」に抜擢された地だ。その前は,地中海・黒海世界の広い地域に様々な民族的・文化的バージョンで存在した古代ギリシア文明圏の一都市「ビザンティウム」である。街はローマ帝国の壮大な“権威”を譲り受け,ローマ皇帝の支配を宗教的に支える「コンスタンティノープル世界総主教座」を擁する重要な“役職”を付与された。だが,イスラム教の聖戦軍の勝利でローマ帝国もキリスト教の時代も終焉しても,どちらも“放逐”はおろか,“御役目御免”にもなっていない。スルタンは同じ土地で,ローマ皇帝の権威の上に乗っかった。教会機構も今後,ローマ帝国の拡張棟だった東方だけでなく,昔の母屋であり,キリスト教世界のままの西方をも征服するため,保持は必須条件だったのだ。そして,存分に利用した。 しかもオスマン帝国だけではない。北のモスクワ大公国,東にいる遊牧系のカラマン君侯国,西からは西欧人らが,皆似たようなことを考えていた。「同じ正統なオーソドックスと皇族との縁戚関係」「普遍のカトリックと古代ローマ」「最後の預言者が説いたイスラム教とアナトリアの地」というそれぞれの主張する絆を旗に,亡きローマ帝国の物的・精神的遺産を勝ち取り,それぞれの自国のため,地域の覇権を欲したのだ。 |
オスマン帝国終焉にまでいたる5世紀近くの間も,このせめぎ合いは様々なバージョンで続き,帝国主義を背景に頂点に達した。結果イスタンブールには,おもに各派の教会を通じ,それぞれの痕跡が残ることになった。戦いの本当の終焉は,「現代」という,誰しもに理性を余儀なくさせる,新たな秩序の到来でもたらされている。オスマン帝国はローマ帝国の真の後継者でありながら,こうした難儀を甘受し続け,命尽き果てることで解放されたのだ。それでもこの間,“他者”たちを鷹揚に受け入れ続け,一方では,“同一の自己”を分かち合いながら“他者”にほだされ,内部から祖国を裏切ることになってしまった異教徒たちを,我が身が崩壊する直前まで,同胞として容赦し続けた。「寛容さ」でなくて何であろう。 “同一の自己”との私の表現は,アナトリアに7世紀以降アラブ系,11世紀以降トルコ・イラン系のイスラム教徒が入って来た頃から,「異教徒」どうしの阿吽の調和と連合,改宗や通婚による融合が現実になっていたことの譬えである。現代の価値観では“裁け”ないことで,人は様々な理由からいつでも改宗でき,別のアイデンティティに移れた。歴史の様々な段階でどの集団が拡大し,縮小し,様々な理由で相互間のバランスを変え,今は「トルコ共和国の人々」として暮らしているのか。こういったことも,トルコのみならず,地域の現代事情を考える上では重要なのだ。 内部の当事者間では,明確な“線引き”の概念はなかったかもしれない。理解しえない,あるいはやはり様々な理由から理解しないのは,むしろ後世の人々だろう。 事実その結果,後に外部からは必要以上に,あるいは人為的な“線引き”が引かれ,一つの祖国や人々を断絶させてしまっている。近代になり突然,当事者間の関係は崩れ,東方のイスラム教徒はヨーロッパ人から見た“アジア人”,離脱したキリスト教徒やユダヤ教徒は“ヨーロッパ人”とされた。今日のEUとトルコの関係にまで及ぶ,“他者”の介入が生んだ歴史上の大きな転換点だ。クルド問題に関しても,ヨーロッパ人はあくまで「トルコ人(!)」との“民族”の違いを強調する。 興奮の渦中にあった時は,そう思った。だが,本当にそれだけでよかったのか。ギリシアや旧ユーゴとトルコの,国内のクルド系と非クルド系の人々の関係にしろ,今,そう再考される段階に入ってきたのではと思う。 |
|
地中海世界と植物7 マスティハ キオスとジェノヴァ/亀長 洋子 |
|
ある島に生える一つの植物が島の歴史を作り出す。マスティハ(マスティック。乳香の一種)とキオス(ヒオス)島は一体となってその歴史を刻んできた。マスティハについては,早稲田大学で行われた地中海学会大会で参加者に配布されたガムとパンフレットでご記憶の方も多いだろう。マスティハは,エーゲ海に浮かぶキオスで栽培されるウルシ科の小常緑樹で,8月から9月の間に採取されるその樹液は家具のつやだしやガムなどとして歴史上利用・愛好されてきた。 キオスは,中世後期の約200年間,ジェノヴァ人の支配下にあった。ジェノヴァ人にとって,この島は交易上二つの重要な意味をもっていた。一つは,キオスの対岸のフォカイアから産出される明礬交易の拠点としての位置を占めたことである。中世ヨーロッパの主要工業製品ともいえる毛織物業において,明礬は媒染剤として重宝されたが,中世ヨーロッパではその産地は限られ,ジェノヴァ商人にとってはドル箱商品といってよかった。それに勝るとも劣らず,この島の特産品であるマスティハは,他のギリシアの島々からは得られない魅力的な商品であった。マスティハの生産や流通を統制するために,ジェノヴァ人は格別の配慮をした。14世紀半ば頃,ジェノヴァ人有志がこの島を征服したさい,本国ジェノヴァ政府との間でこの島の統治についての協定がかわされた。この協定の内容は,居留地行政の代表者から料理人に至るまで,キオス統治のための各種官吏の任務や俸給 |
などについての規定が多く占めるのだが,そのなかで,マスティハについては専門役人がおかれている。彼らは現地のジェノヴァ人支配層によって任命され,政府派遣のキオスの最高権力者であるポデスタやその支配下の官吏とは別の独立した存在と規定され,マスティハの収集・保管・委託の任務を負い,この作業に従事する労働者を使役することができた。 マスティハの産地は島の南部にあり,メスタ,ピルギ,カラモーティ,ハルモリア,オピンピといった村々がマスティハの村として知られているが,メスタには,今も中世の防備集落が史跡として残っている。マスティハやその生産技術を独占したいジェノヴァが,外敵からの襲撃を恐れて,農地のすぐそばにマスティハ生産農家の防備集落をつくらせたといわれる。筆者はキオス調査時にここを訪れたが,狭い路地とすぐに袋小路に至る密集した集落は,外敵が侵入しても逃げ道はないという様子を十分感じさせるものであった。 マスティハの樹液は,現在は薬効や美容効果なども指摘され,キオス島訪問者は,ガムを筆頭に,各種食品類・美容品類など数々のマスティハ加工品を購入することができる。古のトルコのスルタンならずとも,観光客はマスティハのガムの感触を楽しめるというわけである。中世から何百年のときが過ぎた今も,マスティハは,キオスという島の象徴として,今も独特の存在感を示しているのである。 |